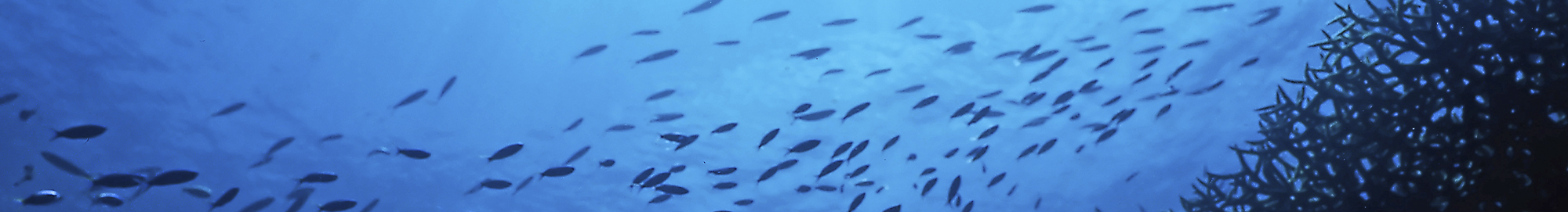魚やエビのぬめり。鮮度が悪い証拠?ぬるぬるする理由は?
魚のヌメヌメ、エビのヌメヌメは生きるために必要な仕組み!
魚を持つと粘膜・ヌルヌルネトネトがビヨーンと伸びる場合があります。
美味しそうではないし、美しい様子でもないのですが、魚の体にはもともとネトネトがあります。
何のためにあるのでしょうか?
①狭い場所に潜るときに怪我をしないように
水が沢山あるように見えて、海底には岩がゴロゴロ。
潮が引いた時に鳥が獲物を狙っている様子を見ると、ゴロゴロ具合がわかります。
このすき間にウナギなどは隠れています。
岩陰に隠れる時に体の表面がヌルッとしているとケガをしにくいのです。
隙間の他、ジャリなどに潜ります。
②水流を滑らかにして泳ぎやすくなるように
ヌルッとしていると、泳いでいる時に水流が邪魔にならずに、早く泳げたりします。
そのため、ヒレや体がヌルヌルしています。
③身を守るため バイキンや寄生虫が直接付きにくくなる
ヌルッとした膜が身体全体にあると、バイキンたちは一旦そこにくっついて魚の体に直接触れません。
そのことで病気になりにくくなります。
マスクをしていると風邪をひきにくい事に近いでしょうか。
ヌルッとした粘膜も定期的に水の中に流れて行けば、体にバイキンが付かない事になります。
鳥の糞が頭に落ちた時に、帽子をかぶっていてよかった!という記憶がよみがえります。
④貝の外套膜はヌルヌル。貝殻を作り出す役目もある!
少しずつ大きくなることで貝殻に年輪ができるのは貝の特徴。
貝殻はヌルヌルの外套膜で少しずつ作られています。
⑤鮮度が悪いと、ぬめりは増える
今までの理由からぬめりがありますが、普段はそのヌメリは泳いでいるうちに千切れたり取れたりします。鮮魚として動かなくなると、ぬめりにバイキンが溜まったりすることで匂いが出てくることも。
基本的に水道水で流す事ができるので、しっかり流せば心配ありません。
ちなみに、口の中も開けて歯ブラシでこする事で生臭さが軽減されます。
ちょっと眺めに保管したい場合はしっかり洗った後に水分を拭き取って保管しましょう。
結論:ヌルヌルは鮮度が悪いためだけではなく、もともとある!
ヌルヌルは生きるために必要な部分です。もともとあるので鮮度が悪いからとは限りません。
一方で、鮮度が落ちると、ヌルッとした感じが強くなります。
そして、このヌルヌルには海水やバイキンが入り込みやすいので、さばく時は最初に真水で流したり、歯ブラシなどでこすったり、塩もみする事でぬめりを取ることが多いです。
ギマのようにヒレだけにぬめりがヒドイ場合はハサミでヒレを切ってしまったりするとさばくのが楽になります。
あ、タコのぬめりを取る場合は、塩もみせずに、ゆでてから歯ブラシでこするのが楽ちんです「こちら」。
では!