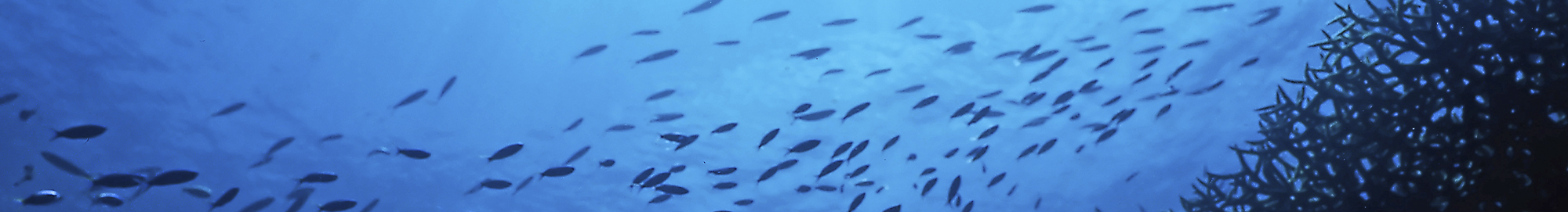鮭が取れないその理由 温暖化?見えない海の中をどう知ればいい?
サケが不漁の理由・原因は温暖化??
全体的に鮭(秋鮭=シロザケ)の漁獲量が落ちています。
25万トン近く獲れていた漁獲量は5万トン程度に減少しています。
獲りすぎではなく、温暖化の影響が非常に大きいと考えられています。
海の水温が暖かくなるとなぜシロザケが獲れなくなるのかを知るためには、鮭の生活する場所や生き方を知る必要があります。
鮭の一生(京都での一例) 詳しくは「こちら」
鮭は10-12月に川を遡上して産卵し、川で生まれた稚魚は、4月頃に海に降ります。
その後、2-8年後に川に戻って産卵します(中には9年後に帰ってきた鮭も。ウロコで計測するそうです「こちら」)。4歳で遡上する個体が一番多く、産卵後は死んでしまいます。
寒くなるまで河口付近でウロウロしながら、少し寒くなってきた時期に川を遡上します(京都で11-15℃、北海道で5-8℃)。
湧き水の近く(凍りにくく、水温が一定で成長しやすい。)に産卵され、卵の育つ平均水温は京都で約10℃、北海道で約8℃です。孵化後に海に降りる水温はいずれも15℃前後で、地域や成長度合いによって生活しやすい水温が異なりますが大人の鮭が生活できる水温は5-20℃ぐらいです。
※植物の開花時期などと同じように、卵から孵化する時間は累計水温となることが多いので、早めに孵化してしまうことで海の水温が寒過ぎて生き残りにくい可能性なども考えられます「こちら」。
鮭自身が好む水温が合わなくなった?
母川回帰(ぼせんかいき)は生まれた川に戻るという意味合いで日本のシロザケ(秋鮭)はほとんどが生まれた川に戻りますが、他の種類では別の川で産卵する割合がシロザケよりも高くなる場合もあります。
母川回帰する事で確実に産卵できる場所を確保できる(生まれて帰ってきた自分がそのイイ例!)という事ですが、産卵のために遡上したくても、水温が高すぎると代謝が高すぎて産卵場所に行くまでに力尽きてしまうかもしれません。そのため寒くなるまで河口付近で待つのですが、サメに捕食されたり、時間切れで力尽きたりとなる事で本州での漁獲量は減ってきたと考えられます。
令和6年の時点では北海道よりも本州で漁獲量は減少し、北海道でも北と南では南の漁獲量が減少しています「こちら」。全体的に水温が高くなったが、北海道の北部では、まだ鮭が生活できる水温であるという事がわかります。ただ、今後さらに温暖化が進めばそこも同様に鮭が獲れにくくなるでしょう。
シロザケの中に高温でも生活できる個体の遺伝子が増えてくれればいいのですが、やはり急激に温暖化が進むことで追いつかない状況になっているのです。
捕食者の状況が変わった??
鮭自身が生活しやすい水温と同様に、サケを食べる魚に取っても水温は重要です。
美味しそうなエサがあっても、自分が動きにくい水温・生き残りにくい水温だとしたらその海域には近寄りません。今までは寒くて鮭がいる海域にはいなかった捕食者が、温暖化によって
温暖化による天敵の増加?①サバ
海に降りた小さな鮭の稚魚の天敵はサバなどで、海に降りたタイミングでサバの群れがいた場合、食べられてしまいます。
海水温が高めの2019年に海に降りた4年後の2023年にシロザケ漁獲量が減少したり、2015年以降、岩手県では稚魚放流時期にサバが多く獲れている事からも、この説は有力です。
最も生き残りやすい戦略として母川回帰に特化して産卵場所を変えないシロザケにとって、水温が変わったとしてもその付近に戻る事で、孵化後に今までは会わなかった天敵に出会う確率が上がってしまい生き残りにくくなってしまったという例です。
温暖化による天敵の増加?②大型捕食者
ある程度大きくなった鮭はサバに食べられる事は無くなります。
稚魚時代は小さすぎるけれど大きな鮭は大型捕食者にとって良いターゲットです。
モウカザメ(ネズミザメ)は別名サーモンシャークと呼ばれるほどサケが大好物。
稚魚放流時期にサバ漁獲データがあり、過去の同じ時期にサバは獲れていなかった等、比較ができないためにサメがサケを食べたのかどうか検証は難しいのですが、シロザケが命を落とす理由がどこかにあるハズ。依然と比較して周辺海域の水温が変化している事、サバや他の魚種が移動している事から、大型捕食者も今までと異なる場所で餌を食べるようになると考えるのは自然なので、鮭が食べられた可能性があるという説です。データが取れていませんが、現在有力な説です。
温暖化による潮の流れの変化で、同じ餌を食べるライバルが増えた??
捕食者だけが、シロザケを減らす理由ではありません。
餌を食べるライバルが同じ場所に移動してきたとしたら、同じ餌を食べるシロザケも減ってしまいます。
北に行けば適した水温になるとしても、無限に北に行けるわけでもなく、どこかでライバルと餌の取り合いになって、直接戦わなくても成長できなくなってしまう事も考えられます。
具体的にはカラフトマスとの餌の取り合いが生じており、カラフトマスが多い年には「こちらの10ページ目」ゼラチン質(クラゲ類)を食べており、カラフトマスが少ない時には甲殻類やイカタコを食べている事が知られています。カラフトマスが多い状態となった結果、今までは成長できた場所で、成長しにくくなった可能性も考えられています。
利根川の例
2024年に親魚の遡上がゼロとなった利根川の個体数減少をシミュレーションした結果です。「こちら」の研究によると、水温だけではなく、栄養が少ない黒潮・黒潮続流と栄養のある親潮が南下しない事によって鮭が泳いでいる海域の動物プランクトン量が減少したことが鮭稚魚の成長と生存に影響を与えたのではないかとの事です。
シミュレーションによると温暖化だけでは説明が付かず、黒潮も大きな影響を与えているとのことです。
鮭を獲りすぎた??
現在鮭の漁獲方法は、陸の近くで待ち構える「定置網」がほとんどです。
場所を変えずに、今まで通り獲っていて、稚魚の放流も行っています。
人が獲ることの影響は当然ありますが、今までと同じ事をしているけれど、一気に取れなくなってきているため、やはり環境の変化が最も影響が高いと考えられます。
魚を獲り続けられるようにしたい!と考えた場合、鮭を獲りすぎだ!という事も考えつつ、他の影響も考える事が重要なのです。
ウナギも同様に、漁獲以外の影響もありますが、なかなか知られていません「こちら」。とはいえ、人の生活も重要なので護岸工事を無くすわけにもいかないというジレンマの中で様々な関係者が知恵を絞っているのです。
どうしたらシロザケを秋の風物詩として楽しみつづけられるのでしょうか・・・。
シロザケ(秋鮭)の食べ方
ひとまず無駄にせず、食べられる部分は全て活用するが誰もができる事です。
「一尾をさばく」のもいいですが、「スジコからイクラをつくる」のも「シラコ」を食べるのもおススメです。
砂利に埋まっても潰れない卵の弾力に驚きながら、鮭の生命力を感じるのはおススメです!
他にも温暖化によるサンマやイカなどの水産物への影響は様々です。「こちら」
一筋縄ではいきませんが、一人一人が温暖化を防ぐ対策を進めるしかないですね・・・。