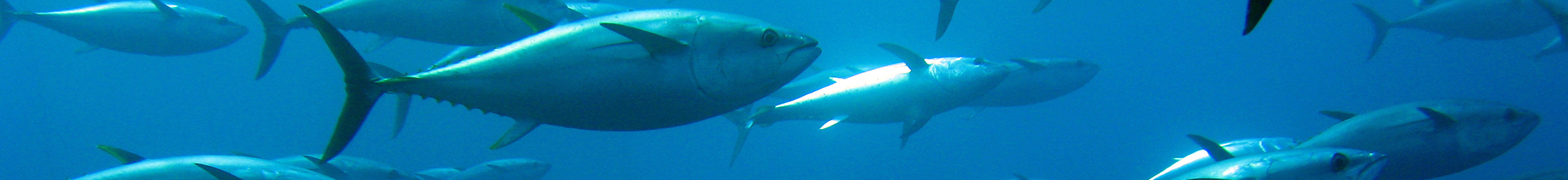貝(イボキサゴ)でおはじきを楽しもう!食べよう!
昔の遊び おはじきは昔、貝で遊んでいた?
指で弾いて当てて遊ぶおはじき。
ガラスのおはじきで遊ぶ人がほとんどでしょうが、昔は・・・貝や小石、木の実等で遊んでいたのです。
その証拠に栃木県佐野市では、昭和の初めまでおはじきをキシャゴ・キサゴと呼んでいたそう。まさに貝の名前です。
ガラスのおはじきが広まったのが明治終わりごろ(1910年ぐらい)なので、そのころから名前が変わり始めたのでしょうか。
遊んでみた!
ガラスのおはじきで勝負していると、コントロールがうまい人が全部取って勝つことが多いのですが・・・
貝の形が左右対称ではなく、転がる方向が読めず、運が重要な勝負なので、負けた時は・・・貝のせいにできます。
ターゲット以外に当てたらダメ!というルールだと、より盛り上がり、学校に遅刻しそうになります。気を付けて!
おはじきにもなるイボキサゴとは?
減っている地域もありますが、千葉県木更津付近では、砂の中から大量に出てくる巻貝の仲間で、鮮やかな色もあり美しい貝です。
中身をキレイに抜いてあげないと、匂いがするので、しっかり食べてあげるといいですね。
採取方法
※注意!
深場などでイボキサゴが溜まっている場所を採取すると、死んでいる個体が混ざる事があるため、全て食べられなくなる場合も。
↑ツバクロエイの手前の裏っ返しになっている空のイボキサゴまで一緒にゆでると・・・少なくとも砂が沢山入りそう。
というわけで、砂に潜っている生きた個体か、波打ち際で洗い流されたイボキサゴを取ります。潮干狩りで掘った直後に、波で洗いだされたのを獲ると楽です。
十秒程度ザルで砂をかき回せばすぐに20個ぐらい取れてしまいます。
↑1分程度でこの量。簡単に集まるのでキレイな色や模様の子を選んでも楽しい!
ただし、小さなアサリが混ざるので、アサリの赤ちゃんは逃がします。
↓上に見えるのがイボキサゴ。小さいアサリの赤ちゃんにもシッカリ模様がついています。
しばらく置いていると動き始めるヤドカリも逃がしました。
楽をしたい場合は、波打ち際でキレイな模様のどころだけを網の角ですくって集めるのがおススメ。
マテガイも海にいる間に何度かこのようにゆすぐと砂噛みが減ります。
家に帰ってゆでて食べたところ(上のナガラミの食べ方を見てください)、砂が多めで食べにくかったので、洗いながら食べたけれど生きている間に砂を吐かせるのがベストです。
お出汁も潮の香りが強めで美味しかったです(漁師さんによると、冷凍してからだと出汁がよく取れるそうです)が、ゆでる量が多いとしょっぱくなるので注意です。
砂抜き方法、ヤドカリ救助作戦
海で拾いながら頻繁にバケツの底に溜まった砂を捨てたり、上のマテガイのように網などで砂を何度も分けながら採取します。手のひらでザリザリと擦って洗って・・・を、海で行う事で砂噛みが非常に少なくなります。
同時にヤドカリは海に逃がします。
食べ方
大き目の「ナガラミ(ダンベイキサゴ)」と食べ方は同じ。
ゆでて、沸騰したら取り出してヨウジなどで食べます。ナガラミは一個10gぐらいあって食べ応えありですが・・・
イボキサゴは非常に小さいのでとても手間がかかり、2時間程度かけて600個を獲ったところ、300g弱。お腹いっぱいになるのは苦しいところ。
ゆで汁が美味しいお出汁になるので、スープや炊き込みご飯に使うのもおススメ。
イボキサゴのおはじきを作りたい!
美しい貝殻を拾って集めてもいいですが、穴が開いていたり割れていたりするため、生きている貝を集めてゆでて貝殻を集めるのがおススメです。
中身を取った後、潮の香りが多少残っています。
水に沈めてゆっくり混ぜて、ザルにとってゆっくり上下左右に振って水を切り、もう一度水に沈めてから水を切り、乾燥させると出来上がり。
少し可哀そうな気もしますが、漁師さん曰く、プランクトンを食べるので、アサリと餌の奪い合いをするので、ちょっと邪魔者だそうです。
十分な数がいる地域であれば、使う分はおはじきにしても良さそうです。
匂いチェック
乾いたら、最後の仕上げで匂いチェックをしておくと安心です。
片手で握って匂いを嗅いで、匂いがしたら半分にして匂わないのは完成!・・・を繰り返し、怪しい子を排除すると良いでしょう。
縄文時代の貝塚から発見されている!
なお、千葉県の「加曽利貝塚」からはイボキサゴの貝が大量に発見されており貝全体の8割を占めることから、縄文時代に食用にしていたと考えられています。
砂浜で確実に見つけられるので、手間がかかったとしても、生きるための食料として重要だったのでしょう。