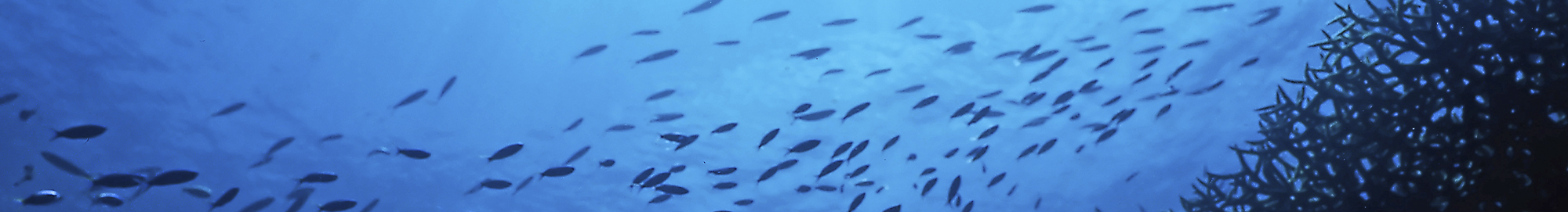家でもできる!切り身を美味しく食べるコツ ドリップって何?
スーパーなどで買った魚介類をちょっと美味しくするコツを紹介します。
レベルが上がったら、「魚を簡単にさばくコツ」もどうぞ。
魚介類全ての共通点
切り身の周りについている水分は、「ドリップ」と呼ばれて細胞からにじみ出した水分です。
細胞が壊れた時に出てきやすいので、断面が多い場合や、解凍された魚はドリップが多くなります。このドリップ、時間が経つと生臭さの他、バイキンが増える原因にもなるので、料理前に拭き取ります。
マグロが超低温で急速凍結されるのは、このドリップが出にくくするためです。急速凍結だと凍るときに氷結晶が細かく作られるため、細胞が壊れにくいのですが、緩慢凍結(ゆっくり凍結)だと氷結晶が大きくなり、細胞が氷の結晶で壊されやすくなるのでドリップが多く出てしまう原因になります。
家庭でドリップの生臭さを減らす方法
塩を振ると水分がにじみ出し、余分なドリップも外に出ます。
そのドリップを、ペーパーでポンポンと拭き取ったり、水でサッと洗って水を拭き取ってから料理すると生臭さが軽減されます。
魚の切り身、刺身用のサク、干物などでも応用できるコツです。
冷凍切り身・干物を調理する方法 解凍する?しない?
冷凍切り身の場合は、よほど大きくて中心まで熱が入らなさそうでない限りは、冷凍のまま調理しても問題ありません。火力は弱めでジックリ中まで火が通るように調理します。
冷凍したまま表面を焼く事でドリップが外に出ない事、凍っている方が形が保たれるので、完成後の見栄えがいいです。
魚種によって異なるドリップ。好みにもよる??
魚種によってドリップ量は異なり、クジラの刺身はドリップが出やすいです。
哺乳類の肉なので、さかなのドリップとは少々性質が異なりますが、おおよその考え方は一緒です。
これは、冷蔵庫で一日ゆっくり解凍した刺身用のイワシクジラ。
真空パックなのでドリップの多さがよくわかります。赤い汁は血ではなく、ミオグロビン(赤い色素タンパク)です。赤身魚はこの色素が多い事で白身魚と分けられます「こちら」。
お刺し身用なので、ドリップ(肉汁)は飲んでも問題なしなので、少しもったいない気もします。
ペーパーで拭いてからスライスしてお刺身で食べます。
30分ほどで食べ終えました。半解凍ぐらいでスライスして食べた場合、お皿はドリップで真っ赤な池ができる事もあるのですが、解凍中にドリップがしっかり出たのか、食べ終えたお皿に残ったドリップはごく少量。
ドリップが出た分、いつもよりも水分が少なく食べやすい気もしました。
少しもったいない気もしますが、ドリップが出るのはデメリットのみというわけでもなさそうです。