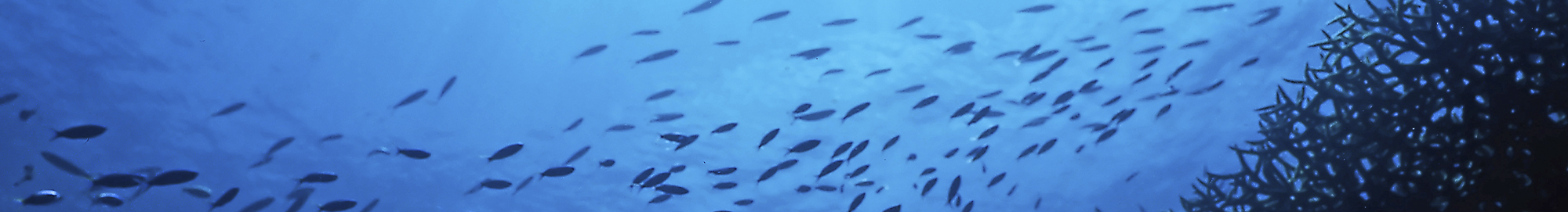赤身魚と白身魚の違い そして・・・青魚と赤魚とは??
赤身と白身の定義!
身の色ではなく、成分で定義されているので身が赤くてもサーモンは白身です。
赤身はマグロやカツオなどの長距離ランナーの魚、白身は短距離・瞬発力型のヒラメやアンコウなど。熱をかけると硬くなりやすいのが赤身なので料理の際のヒントにしてください。
厳密には「色素タンパク質が多く含まれているかどうかで区別され、100gあたり10mg以上あれば赤身魚、なければ白身魚」です(1976年日本水産学会「白身の魚と赤身の魚」による)。
色素タンパクは、色が付いたタンパク質です。
筋肉色素タンパクはミオグロビン(Mb)と呼ばれ、筋肉の中で酸素を取っておくことができます。
血液色素タンパクのヘモグロビン(Hb)は酸素を運ぶ役目があります。
赤身魚の特徴
酸素を運んだり取っておく役目があるタンパク質が多く、体をよく動かす遅筋が発達していることからもわかるように、長距離ランナー型の魚です。
ずっと泳いでいるマグロ、カツオ、サバ、サンマ等で鉄分が多いのが特徴です。
また、カツオやマグロなどのように、熱をかけると堅くなりやすい身質です。
キハダマグロ!
ブリ!手前が腹側の大トロ部分、奥が背中部分。同じ個体でも・・・部位によって色が大分違う。
特に赤い部分が血合い部分で血液・鉄分が豊富。
白身魚の特徴
赤身魚と違って速筋が発達している瞬発、短距離ランナー型です。
エサや敵に対して一瞬の動きが得意ですが、長い間泳ぐのは不得意です。
待ち伏せ型のアンコウやヒラメ、速く泳がないでも毒やトゲを持っていて食べられにくいフグやハリセンボンは白身魚です。手でも捕まえられるハリセンボンのように瞬発力?と疑問になる魚もいます。
イシガキフグ。トゲがあれば早く逃げないでもいいの。
白身魚は熱をかけるとホロホロっと食べやすく、煮崩れしやすくなるのも特徴なのでハンペンや魚肉ソーセージなどは白身魚から作ることが多いですね。
フランス料理のシタビラメとかも白身で食べやすいですね。
鮭、サーモンは白身魚!
鮭やサーモンの身は赤いですが、色素タンパクではなくてエビやカニに含まれるカロテノイドの仲間であるアスタキサンチンの色です。鮭はオキアミなどを食べて赤い色になりますが、白身魚です。
エサにアスタキサンチンが含まれないと白い身になるそうです。
アジは赤身魚!ブリも赤身魚!
アジやブリなど、お刺身で身が白く見える場合も多いですが、血合い肉があるあたりは血が沢山あるため、赤身に近い成分ということになります。
養殖ブリは・・・・白いゾ!これを計測したら・・色素タンパクの割合は低いのではないかしら・・・。部位や太り具合によっても変わってくるでしょう。
青魚とは??・・・定義がない!
アオザカナは赤身や白身と違って、外から見た時に背が青く見える食用魚を指します。
アジ、イワシ、サバなどが代表的です。
マイワシ、ムロアジ、ゴマサバ、サンマは確かに青い!身は赤身が多い印象です。
が・・・青い魚をすべて青魚と呼ぶかというとそうではありません。
青い熱帯魚は青い魚だけれど、俗にいう青魚とは違いそうです。
マグロは青魚?
背中が黒から青なので青魚と呼べそうですが、普通は青魚とは呼びません。
だって・・・マグロで通じるし・・・一尾で買う事ってナカナカないし・・・。
そのように考えると、青魚には「値段が安めの大衆魚」という意味合いも含まれますね。
安いからと言って鮮度が悪いというわけでないのも嬉しいトコロ。
青魚がダメなの・・・。
たまに「青魚がダメなんです」・・・と相談してくる方がいますが、そもそも青魚って何?と聞くとタジタジとさせてしまったりします。そして、何がダメなのかしら?と返事に困ってしまいます。
青魚はEPA等の魚油が多いので、その香りなのか、赤身魚のことなのか・・・。
結局は、定義がない青魚の事なので、その人の気のせい・勘違いの場合が多い気がしますが・・・。
改めて青魚の何がダメなのか、雰囲気や勘違いで決めつけていないか、確認してほしい!
おいしい魚だらけですからね。
赤魚(アカウオ)とは?
赤身魚は身でしたが、赤魚(アカウオ)は外見の色で判断されます。体が大きめで赤い魚が呼ばれる事が多いです。
キンメダイやマダイもアカウオと呼べそうですが、その他大勢の魚で販売するよりは、付加価値が付く名前でわかる魚の場合はキンメダイ、マダイ等のように名前で呼ばれます。逆に、日本名が無いような魚は「アカウオ」として売られている事が多いです。
深海の魚は赤い魚が多く、浮力を保つために油が多いので美味しい事も忘れないで下さいね!
あぶらが多くて美味しい理由は「こちら」
魚の色が沢山ある理由は「こちら」
赤身か白身か、悩んだらどうすればいいのか。
赤身か白身に無理に分けないでもいいでしょう!
何しろ魚は3万種もいるので、それを半分に分けたとしてもそこまで意味はありませんし、ハリセンボンのように、モタモタ泳ぎ、瞬発力なんてあるの?と言えない白身魚もいます。
でも、熱を掛けると固くなる傾向がある赤身か、柔らかくなる白身かは、メニューを考える時の参考にできると思います。
一匹一匹を見てあげて、おいしさや形を愛でて頂けると・・・嬉しいです!
よし!差別せずに魚を食べよう!という気になった方は「こちら」から魚をさばきましょう!
同じように似ているけれど違う似たものシリーズ 他の話題は「こちら」から!