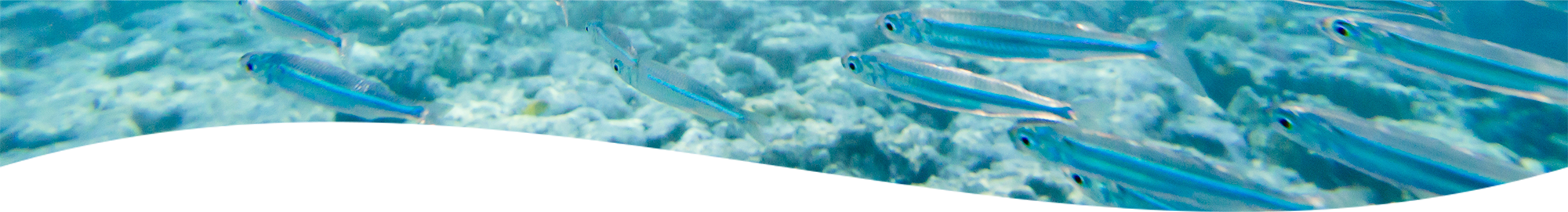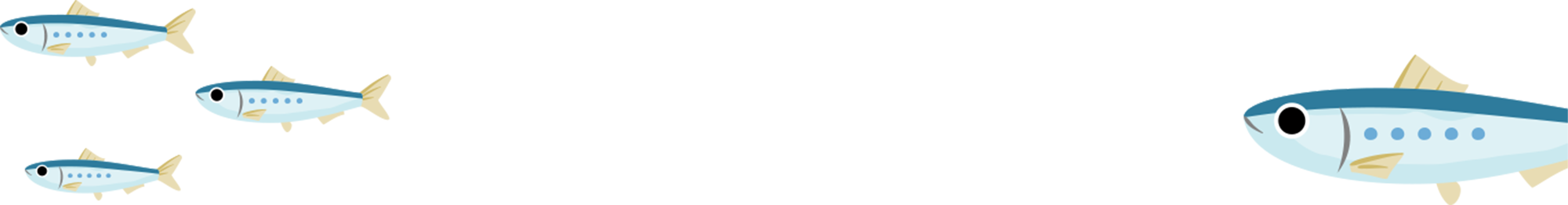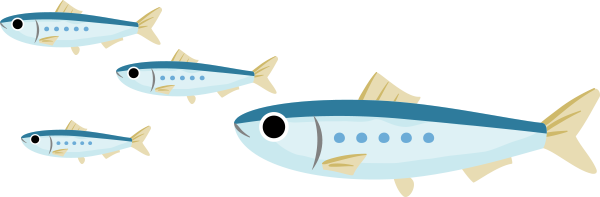廃棄食材で育てた昆虫を養殖魚に与えて育てると、環境にやさしい?
エ?と思うかもしれませんが、数分だけ時間をください。
ゲ!と思う事が、実は地球を救うかもしれません。
魚が虫を食べるのは当たり前!
川魚を釣る人でフライフィッシングを知らない人はいません。フライ(ハエ)のような形に見立てた毛鉤(毛ばり)で、ニジマスやイワナを釣ります。
サメが魚を食べるように、魚を食べて大きくなる種類もいれば、海藻を食べる魚、プランクトンを食べる種類、海底のゴカイを食べる魚等々がいます。
ミミズという名の陸上の栄養は・・・ウナギの大好物。
あいつらそんなものを食べているのか!とビックリするかもしれませんが、生き物にとって、利用できる周囲の栄養(資源)を効率よく集められるかが生き残る秘訣です。
人にとって見た目が微妙でも、命を次につなぐのが重要なのです。
生命の体は、生物変換機!
私たちの体は、食べたものから移動してきた栄養素でできています。
草を食べて大きくなる牛も、草のタンパク質等を体の中のお肉に貯めていきます。
魚達も同じで、養殖魚の場合、カタクチイワシ(アンチョビ)を乾かした魚粉や、大豆などの粉を固めたエサを使って育てています。
そのおかげで、我々はブリやタイ等の見慣れた魚をお寿司やお刺身として楽しめるのです。
ペットの栄養源として利用されている昆虫。
実は、メダカや熱帯魚の他、カメ、トカゲには餌として昆虫が製品化されています「こちら」。
彼らが昆虫を食べても、おかしくないはずですが、「君は栄養のためにコオロギを食べられるか?」と問われると、少し悩んでしまいます。
イナゴの佃煮とハチノコは食べたことあるけれど、コオロギは食べたことない。
虫を与えて大きくなった魚を食べる
人にとってハードル高めの昆虫食も、間に魚が入ってくれたらどうでしょう。
虫を乾かして粉にして、ラムネのような餌にして魚に与えるという事です。
ミズアブの粉を与えて育った魚(マダイ)を実際に食べてみたところ、見た目も味も全く変わらず、普通に美味しかったです。
虫から育ったタイと考えると、うーんと感じるものの、川魚は虫を食べているなら同じ事か。
「ワレカラ」を食べている魚も沢山いるし、人によってはタイの口に潜んでいる事がある「ウオノエ君」の方が怖いかな?
↑アマモに沢山潜むワレカラはエビと同じ甲殻類。この後食べたら美味しかった!
↑鯛の口から出てきたウオノエ。オスメスセットで出てくる事が多いので、実は縁起物!カッコいい!硬いけれど焼いて食べるとなかなかイケル!
人によって見た目が気持ち悪いとか、カッコいいかは違うので、結局はイメージに囚われているだけ?とも思います。
とはいえ・・・気になることも事実。ちょっと意識を変えて、ポジティブな面を見ていきましょう。
ワザワザ虫を使って魚を育てる意味がわからない!
そんな人にこそ知ってほしい、今の地球や日本の状況。皆さんの生活にも関係してくる問題です。
世界を救う??アメリカミズアブは全世界で栄養のバトン役になれる
ミズアブは全世界に住んでいて、生ごみなどから発生します。
食品残渣はどの国でも発生しているので、現在使いにくい栄養分をミズアブに変換してもらうのは良い考えに思えます。
捨てている食料を生き返らせる!食品ロスと食品残渣の違い、年間重量(平成30年)
食品ロスは外食産業や一般家庭で出る「食べ残しや消費期限切れ」の人が利用できたであろう食べ物で、年間600万トンと計算されています。
食品残渣は食品工場などで出る、人が利用するには難しい部分で、固いキャベツの芯や色が悪くなった部位で年間2500万トンと計算されています「こちら」。
どちらも人が食べる前提で生産されているので農薬等の問題はありません。
この食料を生き返らせてくれるのがミズアブ君。キャベツの芯等を魚が育つ粉に変えるための歯車になってもらいましょう。
人が利用できなくなった部分をミズアブに与えて増やすと・・・仮に500万tをミズアブに与えると、20万tのタンパク質の粉、そして油ができる計算になります。
餌の値段が急上昇!→養殖魚の値段も高くなる!
世界人口が増えており、タンパク質が足りないため、養殖を始める人が増えたりすることでライバルが増えて、養殖魚のエサ値段が高くなっています。
養殖魚の値段の6割がエサ代。今後さらに高くなる可能性があります。
天然魚のアンチョビは毎年獲れる量が変わり安定供給が難しい年が出てくることもありそうです。
そう考えると、海外から餌を運んでくるよりも、国内で安定供給できたほうが良さそうですし、結果として養殖魚の値段が抑えられそうです。
文化を変えないで済む!
牛より豚、豚より鶏の方が環境負荷が低い。さらにコオロギの方が負荷が少ないという声を聞く事があります。世界人口が増えすぎてしまった事が一因です。
肉を食べずに大豆を食べよう。コオロギを食べようという意見もわかりますが、普段の生活も変えたくないし文化も守りたい。
そうなると虫ではなくて、見慣れた魚に変える事が現在の文化を守りながら生活できる事につながります。
二酸化炭素排出量が防げる!
海外から養殖に必要な魚粉を運ばないで良くなるので、その分二酸化炭素削減につながります。
海外から20万トンのタンパク質の粉?1万コンテナ!と考えると、なるほど!と思えるのではないでしょうか?
新たな雇用の創出
ゴミではなく資源を集める、地球を守るための仕事が増えます。
そのことで今までは海外に払っていたお金が国内に使われ、その地域が元気になります。
海外からまとめて運ばれてきていた分を作り出すのに、食品工場などから餌作成工場へ運ぶ仕事、餌作成工場の仕事ができます。
タンパク質が足りないこれからの世界。どうなっていく??
人口が増えすぎて、絶対量が足りないため、食べ物の価格が上昇しています。
その一つの可能性。
養殖魚のエサとなるアンチョビは・・・アンチョビは魚のエサでは無く、人が食べる方が効率がいいのでは??となると、より一層値段が高くなり、養殖魚のエサが無くなる事は必然とも考えられます。
↑フライがとても美味しい!アンチョビ。@ペルー パイタ
人が利用できる食べ物はそのまま人が食べて、人が食べにくいものは一旦他の生き物に食べさせて人が食べられる形に変わってもらう方向になるのではないでしょうか。
SAF用の燃料になるかもしれない
実はムシアブ君、タンパク質の粉だけでなく、油もとれるので、それを使えばカーボンニュートラルな燃料となる事もメリットの一つです。温暖化を防ぐ飛行機燃料:SAF燃料とは「こちら」。
こちらも有効利用できるといいですね!
これから考えなければいけない事
以前はお金を払ってゴミとして持って行ってもらっていた食品残渣は現在はお金を受け取って引き渡す形になっています。
お金を払って持って行って、飼料に生まれ変わって活用されているので、新たに魚のエサにしたい!と食品残渣を欲しがる人が増えると、ライバルが増えるので値段が上がる可能性があります。
現在利用している人たちにとっては苦しい状況になりますが、その分今は廃棄されている分がシッカリ集められるようになる可能性が高いです。
技術の進歩と共に、より一層無駄なく活用できるかもしれません。
皆さんへのお願い
ギョッとしたかもしれませんが、技術が進んでも、理解する人・買う人がいなければその技術は広がりません。
色々な考え方があるんだなぁと、まずは、「いやだ!」ではなく、「ヘェー」と感じてみてください。
ムシアブは嫌だけど、カマキリやミツバチなど別の虫ならいい!等も人によって違うかもしれませんね。
閲覧注意ですが・・・釣り人は見慣れているイソメ・ゴカイたちも海の栄養を貯めて魚にバトンタッチする生き物です。
ミミズと同じ役割として可愛いと感じるか、気持ち悪いと感じるかは・・・人それぞれです。
見慣れた人にとっては「魚が釣れそう!いいイソメ!」でしょうか。
ミミズやらイソメやら、魚を食べるたびに、わざわざ思い出す必要はありません。
食物連鎖によって栄養が命によって運ばれる事を考えると、気持ち悪いと感じる事も無くなるかもしれませんね。