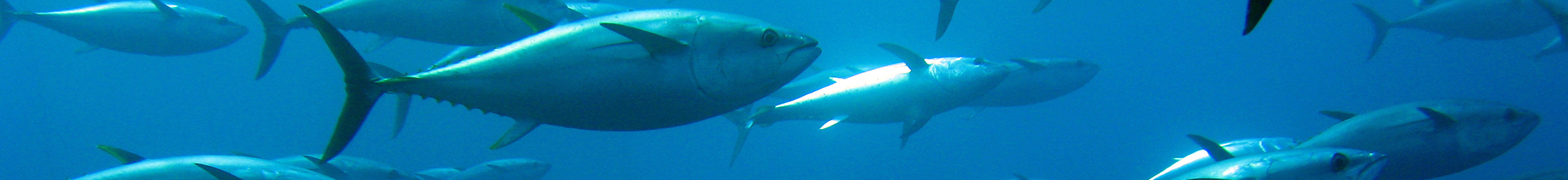フグ毒 食中毒を考える しらす干しやチリメンのフグの稚魚は??
フグ毒
「フグは食べたし、命は惜しし」、「鉄砲」、「北枕」等の言葉からもわかるように、毒が有名なフグ。
フグが食べたモノから毒が体内に溜まります。そのため季節、個体、地域で大きな差があるのがフグ毒の特徴です。
フグの毒は種類によって皮、肝等毒が溜まる場所が異なるため、調理には免許が必要です。
多くが自分でさばいた場合の食中毒事例であることも特徴です。一回大丈夫だったから・・・ではいつか鉄砲に当たるかも・・・・。
釣りなどをしない限りは、普段は気にしないでいいのですが、たまに「混入」という形で耳に入る場合があります。
食べてもいいの?しらす干し、チリメン、煮干し内のフグの稚魚
シラスを取るときに、タコやイカの他、同じぐらいの大きさの稚魚たちが一緒に紛れてしまいます。
手のひらの上のフグの赤ちゃん@6月の三宅島の漁港にて夜に採取。
季節や個体によって毒性が異なるので、「食べない」が前提です。見つけたら脇に寄せて食べないようにしましょう。
「食べない」が前提だけど・・・気づかぬうちに食べても大丈夫??
そもそも卵が1‐2ミリのフグは、生まれたばかりは3-4ミリ。色々な魚の胃袋に入っているかも?等と考え始めたら魚も海藻も何も食べられなくなり現実的ではありません。
びくびくしすぎて、しらす干しを一切食べない!とならぬ様に、一つの考え方「例」をお伝えします。
季節や個体、地域や大きさなどによっても異なる他、気象条件によって想定外の事が生じる事もあるので注意は必要です。
ちりめんじゃこ、豆アジパックへの混入とその毒性、10MU/g以下のものは人の健康を損なう恐れが無い事も紹介されている、魚介製品へのフグ種の混入事例についての報告書は「こちら」から。
報告書によるとしらす干しに混ざる大きさの、トラフグやクサフグの稚魚の毒量は1ng程度と極めて微量で、成人の致死量はその100-200万倍とされています。
なので、しらす干しと一緒に誤ってフグの稚魚を食べてしまっても、健康への影響は極めて低いと考えてよさそうですし、フグの稚魚に触れていた隣のしらす干しも大丈夫と考えてよさそうです。
※2024年~厚生労働省の補助金「自然毒などのリスク管理のための研究」においてフグ仔魚の安全について研究中です。期待したい!
しらす干しの中から見つかるフグは20㎜程度、マメアジに混ざっているフグは40㎜程度等、群れによって混ざっているフグの大きさも異なりそうですが、購入時、調理前、食べる前に、自分の目でも見て確認しながら食べれば安心です。
※鮮度が大事な魚は、悪くならないようにどんどん仕分けますが、慣れているプロとはいえ人の目です。イワシの中にサバが入ってしまうこともあります。
↑「あの~サバが入っていますけど・・・」と話しかけたら「失礼しました!」と捨てられそうになったので、「いえ、イワシと同じ値段で買いたいです!」と伝えて買わせてもらいました。
冬の港で寒い中、仕分け作業をしたのだろう・・・と考えると、捨てるなんてとんでもない!
フグが丸ごと製品に入っていたらダメ?
毒があろうがなかろうが、食品衛生法上、フグは毒がある場所を取り去ってから一般に流通させないといけません。一匹丸ごと入っている稚魚は、いかに小さくても販売禁止です。そのため、害がないとしても法律上は販売禁止=回収という構図ができてしまいます。
法律は法律ですが・・・。自然のモノなので難しいところです。
この大きさより小さいフグは安全!等のルールがあると現実的なのですが、ありません。
そして「フグだーーー」と大声で叫ぶ人が多いほど、リスクのある商材を扱うお店が減っていきます。
しらす干しやチリメンにフグが入る理由は?
一言でいうと「海の豊かさ」のためにフグの赤ちゃんが混じることがあります。
春になると太陽光が強くなり植物プランクトンが増えて餌が増えて生き残りやすくなるので生き物は盛んに産卵し成長しようとします。
そのタイミングで同じぐらいの大きさのシラスを取ると、同じタイミングで大きくなろうとしているイカやエビやフグが混ざってしまう場合があるのです。
日本の海の近くは魚の種類が多く、魚の群れは一種類だけとは限りません。怖がりすぎず、海の力を感じながら、しらす干しを食べてほしいです。
私が30年前にしらす干しを食べる時は、タコやエビの稚魚を取っておいて、最後にまとめて食べるのが楽しみでしたが、最近のしらす干しはシラスしか入っていませんね・・・。
風力選別機により、風で飛ばして重さでシラスとそれ以外を分けて、色彩選別機で色でチェックして、人の目で目視確認等を昔よりもしっかりと行うことで、しっかりと見ているからです。
これを繰り返すたびにコストがかさみます。
皆で不幸にならないために・・どうしたらいいのだろうか・・・。
法律上、フグを丸ごと流通させてはいけない!という考えは正しいとも言えます。
人が食べる食品を責任もって作る以上は、シッカリ選別させたうえで完璧なモノを出せ、という考えは正しいですが、現実的にはナカナカ酷な話でもあります。
カンペキを求めていない時代はある程度余裕があった法律も、厳密にする傾向が強くなってきている現在は、売る側も買う側も全員が不幸になる方向になっている気もします。
漁師さん:売れない魚は獲りに行かなくなる。
加工屋さん:混入を防ぐために頑張るが、手間が増えるので値段は高くなる。手間が増える分、生産量が落ち、出荷量が減り、漁師さんから今まで通りの量を買えなくなる。
流通(スーパー等):値段が高くなったが・・・人の目なので「絶対」はない。回収事故をゼロ件にするために一番の方法は・・・品揃えから外すという判断も。
消費者:しらす干しが並ばずに買えなくなるか、値段が上がるか。
モノの値段には理由があるので、今まで以上の事を求めると値段に影響します。もちろん安全のためには毒性のあるものが流通しない仕組みは重要です。が、求めすぎると売らないほうがラク!という方向になります。
何事もホドホドが肝心ということでしょうか。現実を見て、どうしたいか一人一人が考えてください。
アニサキス問題で既に天然魚や刺身の販売が減っています。悲しい!と感じている私がフグを見つけたら・・・・
お店に連絡すると「同じ日のしらす干しをすべて回収!」となる事が想像できるので、脇によけて、乾かして標本にする、ぐらいでしょうか。
フグもカワイソウ!生きたまま逃がせばいいのに・・・・
確かにそうなのですが、生きたまま逃がそうとすれば時間がかかって他の魚の鮮度も落ちてしまうのです。そのため、ゆでて鮮度が落ちないようにしてから目で見てシラス以外を取り出す方法になっています。
煮干しから取り出したフグたち。一番大きいので7センチ。
可哀そうな気もするけれど、このフグたちの分も、しらす干しを残さず食べましょうね。
「フグ毒以外の海の食中毒」も、知ればそこまで怖くないですよ。
なんだか自然の力を感じたぞ!という方は、「魚が生まれて育つためのエネルギーについて」もどうぞ!
マフグの白子。少し崩してお召し上がりください!