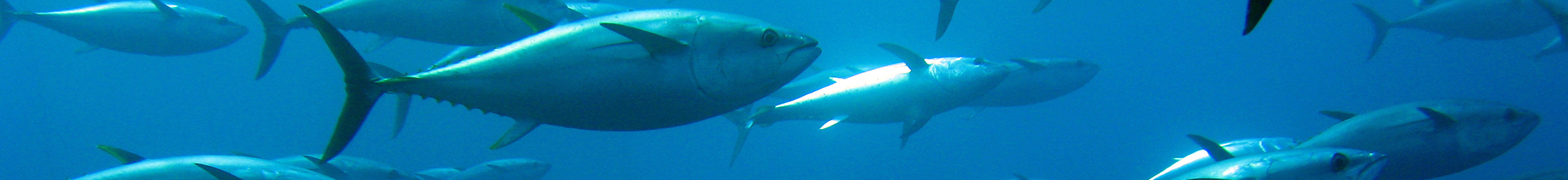水産物の「食中毒」と「安全な情報」を考える
「食中毒」
自然毒、化学物質、アレルギー、寄生虫、ウイルス、細菌等様々です。
食中毒は、腐った食べ物が原因でお腹を壊すと言うイメージになりがちですが、食べた時点では異常が感じられない、見分けがつかない場合も多いため、「かもしれない」と考えて行動することが、食の安全につながります。魚種、鮮度、保管方法、加工方法、地域、季節等々によって条件が異なり難しい分野ですが、人命や健康に関わるため、家庭を含めた広い関係者が知識を増やすことは重要です。
まずは知る事から「安心で楽しい食卓」は始まります!
〇自然毒
⇒鉄砲、北枕の別名があるほどで有名です。免許が無い場合はさばかない事。
「貝毒を代表する有毒渦鞭毛藻(シガテラ毒、パリトキシン、貝毒)」
⇒南方系の魚、大型魚等で、地域によって流通自主基準が設けられていることも。市場を通っているモノは安心です。
⇒さばいたときに簡単に取れます。さばいてみてください。
〇化学物質
⇒偽アレルギーとも呼ばれ、判断が難しい物質です。魚が関係するのは①ですが、しっかり冷えて管理されていれば、まず問題なしです。
①子供にとって必須アミノ酸のヒスチジン。これが細菌によって分解されて生成されます。
②花粉症や食物アレルギーによって体内のマスト細胞がヒスタミンを放出してかゆくなります。
③発酵食品が発酵される間にヒスタミンを生成する場合もあります。
〇アレルギー
「アレルギー」は食中毒か微妙ですが、体内でヒスタミンが合成されることでヒスタミン食中毒との見分けは困難です。また、アニサキス食中毒とも関連するため、症状が出る場合は何が原因か調べたほうがよいのですが、個人差があるので判断が難しいです。
〇寄生虫
大きく体の外に付く外部寄生虫と体内に入り込む内部寄生虫に分かれます。
寄生虫は、どれもホスト(宿主:しゅくしゅ)から栄養や住処を提供してもらう形で生きています。宿主を駆逐してしまうほど害を与えてしまう寄生虫は種として存続できなくなるため、基本的に寄生虫が宿主へ致命的な害を与えることは少なく共存しています。ただ、本来のルートと異なる生物の体内へ入った場合などに寄生虫が宿主に害を起こす場合があります。
魚の場合は、件数から考えてもアニサキスとクドアをシッカリ理解すれば、大半の寄生虫は防げます。
冷凍、加熱が確実な予防で、目利きは見てわかります。最初は確実に「時短料理につながる冷凍刺身!」がおススメ。5分でいつでも刺身を楽しめるようになります。
各自の判断で安全に食べる方法を紹介します。
「アニサキス」 自信がない人は冷凍すれば怖くない!お酢は効きません!
「クドア」 最近発見された寄生虫で目に見えません。ヒラメだけ気にすればOK。
「その他」 見た目だけで健康被害がない寄生虫も紹介。ただし、淡水生物には注意です。
〇ウイルス・細菌
「ノロウイルス」 手洗い不足が一番の原因。牡蠣のイメージに囚われていると危険です。
「腸炎ビブリオ」 過去20年で1/100に激減していますが・・・
「黄色ブドウ球菌」 魚由来ではないですが、調理している人から・・・
知らないからコワイのです。一つずつ理解していくと、怖くありません。