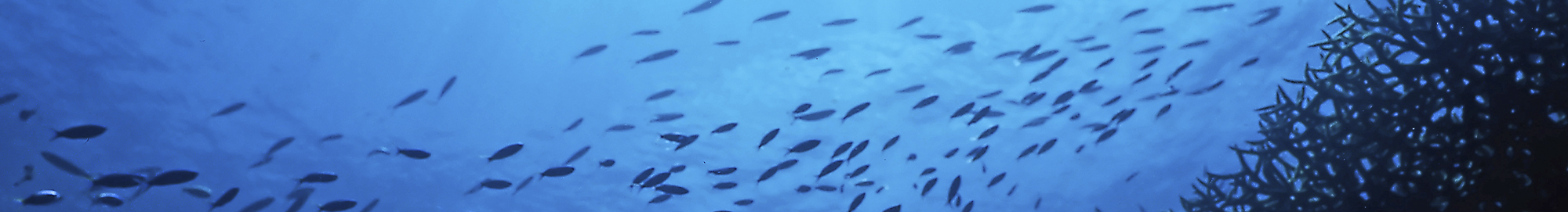買い負けとは 人気が出ると値段(相場)は高くなる!
世界で人気の海産物
日本だけでなく、世界中で大人気の海産物。
美味しい魚を食べて、美味しさを知ってしまった人は、また食べたいと考えます。
今までは食べる人・欲しい人が少なかったのでイイモノの値段が安いままだったとも言えます。
そう・・・。日本の食文化を代表する寿司や刺し身、魚達がとてもおいしい事を、世界中の人に気づかれてしまったのです。
需要が高まると、物価は上がります。食べたい人が増えて、モノの量が変わらなければ、値段は高くなるのが・・・この世のルールです。
人口が増えるだけでも単純に物価は上がるハズですが、人気が出るとさらに値段が上がります。
和食文化が知られる事は嬉しいのですが、値段が上がるのは悲しい気がします。
「買い負け」とは
セリやオークションと同じで、売る側は高く買ってくれる人・国に売ります。
買おうとしても買えずに負けてしまう事を「買い負け」と言います。
相場に合った値段が出せない場合はもちろん、高い値段を提示できても、手間がかかって面倒な場合等で、売ってもらえなかったり、作ってもらえなかったりします。
値段や品質面で条件が合わないという事です。
誰しも自分のモノを高く、確実に、楽に売りたいので、少しでも条件がいい仕事が優先されるシビアな世界でもあります。
・・・・結局のところ、イイモノは相場にあった値段を提示しないと買えない、ライバルより良い条件を示さないと売ってもらえない、という当たり前の事になるのです。
買い負け例① カニ
国産の活ズワイガニ@豊洲市場
2005年頃、日本が輸入するカニは、10万トン、900円/Kgぐらいでしたが、2020年は2万tと1/5程度の量に減っています。
減った理由を値段と一緒に考えてみると、この15年間でタラバガニは1Kgあたりが900円から4000円以上と4倍以上の値段、ズワイガニも700円から2000円/Kgと3倍近くの値段になっています。値段が高くなったので買える人が少なくなったので輸入量が減ったということになります。
輸入量が減ると、売る側は来年も買わないだろうと日本以外の買ってくれる国と話をし始めて、日本の買い付け担当をあまり重要視しなくなります。
そうする事で翌年はさらに輸入量が減る、という悪循環にもなります。
買い負け例② エビ
日本で食べられるエビの95%は海外からの輸入で、実は海外のエビがおせち料理などの和食文化を支えています。
↑冷凍で時間が停まり、刺身でも食べられるアルゼンチンアカエビ。
シーフードミックスや、揚げてすぐ食べられるエビフライは、時短調理ができるような形でムキエビやエビフライ用のエビとして、エビが獲れるインドやベトナムなどで殻を剥いたり粉を付けた状態まで加工してから日本に持ってくることが多いです。
インドやベトナムでは獲った後に殻を剥く作業に人手がかかります。
これまでは手間がかかっても作ってくれていましたが、中国等のように頭や殻が付いたままのエビの方が、殻を剥いたエビよりも価値が高いと考える国の人が、エビが欲しいと買い始めたらどうなるでしょうか?
インドやベトナムの工場の人は、殻ムキをしないで、獲ったままの姿で冷凍して売ってしまった方がエビが早く出荷できます。
加工する人を何百人も集めずに、人が沢山入る工場を建てないでも、冷凍設備さえしっかりしていればコンパクトな工場で出荷できる事になります。
また、今までは殻を剥く手間に時間がかかっていて、沢山出荷できなかったけれど、冷凍するだけなら圧倒的に早く出荷できるので、その分ドンドンエビを仕入れて売ることができます。
となると・・・手間がかかるエビと、冷凍するだけのエビ、どちらを売りたいかは・・・わかりますね。そのようなことで、高い値段だけではなく、手間が多すぎると断られてしまう事もあるのです。
もちろん、手間がかかってもその会社の将来のためになれば大変な作業でも受けてくれるので、それは買い付け担当の腕の見せどころです。
ここで皆さんへのおススメは、「エビ味噌まで食べる方法」身だけしか食べていないのはもったいない!ですし、ちょっと高くても味噌のためにお金を出せると思います。
買い負け例③ ウニ
カニもエビも輸入が多いので海外に買いに行く場合でしたが・・・
実はエビは現地の人はお金持ちしか食べる事ができません。高いので輸出用がほとんどなのです。
これが・・・日本でも見られ始めています。
ウニは国内の市場に加えて海外からの注文が入ります。
その値段に引っ張られて最近では、ちょっと前の倍の値段になりました。
誰もが、高く買ってくれるところに売ります。日本で獲れるけれど日本では食べる事ができないという状況も起き得るのです。
2017年 築地市場にて。現在の相場を考えると、お手軽な値段・・・と感じてしまいますが、昔はよかった・・・と考えずに現在の相場=適正価格も考えて、買うかどうするか・・・
モノの値段 為替と相場
ちょっと前までスルメイカ一杯100円だったのに・・400円なんて高い!
と言っていませんか?モノの値段は、その時欲しい!と考えている人達との勝負です。
そんな例としてイカの値段をご紹介。
アメリカオオアカイカというイカのゲソは、コンテナ(30トンぐらい)単位で1トン何ドルという契約をして購入します。
10年前は一トン500ドルでしたが、2022年は3000ドルとドル価で6倍になりました。
さらにここでドルと円の「為替:かわせ」も考えないといけません。円安だと海外からの原料は高くなるのです。
10年前の2012年の2月の為替は1ドル76円でした。2022年の2月は1ドル115円です。
単純に掛け算すると、10年前は38,000円だったイカの値段が、345,000円と9倍以上になっています。3月末は1ドル124円となったため、372,000円と1-2か月で一割値段が上がったことになります。2022年6月は1ドル135円!405,000円と10倍を超えてしまいます。
2024年11月のゲソは、5200ドル/トンで、1ドル155円と考えると、806,000円!単純に20倍以上の相場です。
関税や加工賃などを考えると、この20倍がそのまま皆さんが食べる時の値段にはなりませんが、イカそのものの値段は、この値段を払わないと買えない状況です。これが世界のライバルが買おうとしている相場です。
そんなに高かったら買わないぞ!と言っても、他の買ってくれる国に売るのでいいですよ。と言われてしまうだけです。つまりは・・・買い負けです。
今まで当たり前に買えていたモノが買えなくなってきているという事実も知って「昔はこうだったのになぁ」というのは意味がないことでもありますが、寂しいですし、なんとかならないのかと感じるわけです。
逆に、スルメイカが100円から1,000円近くなっているのはまだマシ?とも言えますね。お財布との相談ですが・・・。
日本の給料が高くならない問題も?
為替も関係していますが、海外ではお給料が増えているけれど、日本はお給料が変わらないということも買い負けの原因の一つです。
過去30年で日本の平均賃金は変わっていませんが、アメリカは1.5倍、数倍になっている国もあります。
お給料が上がった分で、美味しいものを食べるか・・・旅行に行くか・・・人生を楽しむ選択肢が増える国もあれば、今まで通りで他の国より弱くなってしまう国も出てきます。
このように、世界全体でお金持ちが増えて美味しい魚を食べたい人が増えれば、今までと同じ金額しか出せない国には魚が買えない=買い負けしてしまうということにつながります。
逆に、日本国内で生産される鮮度抜群の多種の魚たちは海外の人にとっても興味があるハズ。
真珠やホタテ、ブリなど以外にも美味しい魚達はたくさんいます。
資源が枯渇しないように上手に獲って持続的に売って行きたいものですね。
食べ物が高くなるのはおかしい?
重要な食糧は国が一旦買い取ったり値段を決めているので、普通はあまり気づきませんが、穀物も一年毎に不作等で2-3倍の値段の差が出ています(農水省の「こちら」に詳しい情報があります。)。
モノが少なくて、ほしい人が多ければ高くなるのは当たりまえの事です。
昔はこの値段で買えたのに・・・と言う事は意味がありません。そのころはバレてなかったおいしさを世界が知ってしまったのです。
そして、マンションを持っていて売ろうかなと考えた時に、値段が安かった数年前のマンションの価格で売れと言われて売る人はいないでしょう。高く買ってくれる人に売りますよね。それと同じです。
そして、相場よりも安い場合は・・・買いたいけれど、ワケアリでは?と考えるのが普通ですよね。
最近は食料の値上げが顕著ですが、世界人口が増えているため世界的な流れで、いい魚は高いお金を出さないと手に入らなくなっていくでしょう。
海産物を食べ続けるには・・・どうすればいいの?
海外からの原料が高くなると、これまで海外品と比較して高く感じていた国内の原料をうまく使えるようになる事もあります。なので円安や相場の上昇が「悪」かというと、そうでい側面もあります。
モノを買うと、生産者の給与になり、会社や工場が新しく設備を投資できるようになります。
そのように考えると、どのようなモノを買うのがよいか、そして一人一人の工夫でオイシイ魚を食べ続ける事ができるようになりそうです。
魚で言えば、お給料が上がって漁師が増える事で、日本の漁業が元気になって魚を獲る人が増えるでしょう。
そして、手間と考えずに上手に食べる事もポイントです。
・自分でできる事は自分で!
エビは好きだけど、自分ではさばけないと言っていると、日本でとれたエビも全て海外に売られてしまう状況になるかもしれません。自分でできる事はなるべく自分で。その方が値段も安くなります。
・無駄なく食べる
エビの頭を捨てるとそれだけで半分の重さになります。お味噌汁にしましょう。
イカの内臓捨てていないですか?肝臓こそがオイシイ!軟骨部分もコリコリがオイシイ!
ポイっと捨てそうな魚の骨もスープにすると、1.5倍の量の身が食べられる事になります(アジの上手な食べ方を「こちら」で紹介!!)
鯛もオイシイスープが作れます。
100円のアジが150円になっても、スープが作れるようになれば・・・許せるのでは??
・未利用魚を食べる!
まだまだ知られていない魚介類はたくさんあります!地元で獲れる海産物、ないですか?
セミエビとかゾウリエビとか・・・国産のエビでも知らない種類は多いハズ!
イセエビにも負けていないおいしさでレア!なこんなエビも人気が出る前に食べてみておいしさを知っていただきタイ!
これから5-10年もすれば買い負けがもっと進んでしまうかもしれません。
そんな時に慌てずに、人気が出る前に知っておきたい「未利用魚」については「こちら」からどうぞ!
毎日放送さんで解説しました。「こちら」
買い負けでダメだ!と諦めずに、身近で知らない魚のおいしさを知るきっかけになれば、まだまだお買い得な海の幸が沢山隠れているのが、世界で6位の広さの海を持つ日本。嘆くには早い!
日本の漁獲量は最盛期1200万t→420万トンと減少していて漁師も40万人→15万人と減少しています。
海外向けに売れて魚価が上がれば漁師が増えて・・・皆さんが手にする魚も増えていくハズです。
もちろん、減らないように上手に獲るように考えていくので、皆さんは、残さないように上手に食べてくださいね。