未利用魚・低利用魚とは? 海の資源を上手に食べよう!
未利用魚の定義とは?
よく言えば「地魚」です。利用されないので「未利用魚」、価値がない・価値が低いので「低利用魚」、目的の魚に混じるので「混獲魚(コンカクギョ)」、雑多に獲れるので雑魚(ざこ・じゃこ)、メジャーでないので「マイナー魚」、「インディーズフィッシュ」等、呼ばれ方含めて定義は曖昧です。「低未利用魚」等、さらにミックスされていたりするので混乱しますね。
漁獲量(少ないor獲れすぎ)、手間(コストに見合わないサイズ、トゲなど)、知名度や知識(知られていない魚・さばく知識がない)等々の理由で、ある地域では高級でも、他地域では食べ方がわからない等が未利用魚・低利用魚と呼ばれる傾向があります。
美味しさとは関係ないので、腕さえあれば安く手に入れるチャンスでもある魚達ですが、周囲においしさを気づかれて有名になると値段は高くなるので、腕を磨くのも今がチャンスです!
豊かな海だからこそ発生する?未利用魚
日本近海の豊かな海では3700種類の魚介類が取れて、市場には600種程度の魚たちが並びます。
その中で皆さんは何種類の魚を知っていますか?50種も言えればナカナカのレベルですが、残った550種は売れ残りやすく、未利用魚になる傾向が高めの種類です。
市場の人は食べ方を知っていても、魚屋さんが町から姿を消しつつある今、消費者に情報が伝わりにくくなって未利用魚という存在が無視できなくなってきています。
ただ、今日売れていなくてもメディアに取り上げられて突然人気が出れば利用される魚になります。
ブームとも関係する、農作物で言うとシークワーサーのような存在なので、他の人たちにおいしさを知られる前に、知らない魚こそドンドンチャレンジしてほしいのです。
厄介者の未利用魚??
温暖化で海が暖かいままだと、魚がジッとせずに餌を食べてしまう。それによって「磯焼け」の原因になる海藻を食べてしまう種類を食べて利用してしまえば、海の多様性が保たれて、お安く買えて、売れる!という各方面のメリットが生まれる可能性も。
アイゴ、サンノジ、イスズミ、ブダイ。どれも美味しいです。
駆除するだけでなく、無駄なく食べようという意識が高まれば、ノリを食べてしまうクロダイなどの数を減らすことになり、ノリも収穫アップ!という効果が出るかも??
どんな魚?
よく言えば「地魚」な魚たちは、全国規模では知られていない、その地域でしか食べられない、見極められる腕の良い料理人のお店でしか食べられない特別な魚!とも言えます。通だけが知っている美味しい魚というイメージと考えるとオイシソウ!ではないでしょうか。つまり、「魅了魚!」でもいいハズ。
例えば・・・北海道ではカスベ(エイ)は普通に食べられています。東京だと・・・乾燥させたエイヒレは食べた事があっても、生のエイはあまり知られているとは言えなさそう。
そもそも煮凝り等で食べていてもそれがエイと知らずに食べていたり。
このように、同じ魚でも地域が変われば、売れなくなる場合があるのです。
未利用・低利用な理由
食べられない・売られない理由は様々あり、理由が複数組み合わさる場合もあります。
①知られておらず、売れない。
名前も形も知らないと、買わない人が多いです。
特にヒレが大きいトクビレ。断面が八角形と覚えれば「知っている魚」になり、さらに蟹のような味だと聞いていれば味わってみようと思うけれど・・・知らない人がこの姿を見たら、買いたいか??
奇抜な形や色など、楽しむには絶好の魚が日本の海にはたくさんいるのに・・・・。知れば食べたくなるハッカクのヒミツは「こちら」から。
魚自体は知っていても、その土地だけでしか呼ばれない名前を他の地域に伝えても、何その魚?ということも。「ハゲ」は、一度聴いたら「カワハギ」の別名と覚えやすいけれど、「イラギ」取れたけどいらない?10Kgだけど・・と言われても、アオザメの事だとはわかりません。
②毒やトゲが危ない
高級魚のオコゼは毒トゲを切って売られる有名な魚ですが、「アイゴ」のように地域によっては高級魚だけど、他の地域では毒のトゲが不人気の理由になります。
食べられないためのトゲで美味しい事が多いのに・・もったいない!
ハサミで切ってからならトゲの毒も関係なし。
③数が揃わず、売れない(たまにしか取れない・とれても一匹)
有名なら一匹でもほしい!クエが獲れたらいつでもいいから送って!予約!となりますが、知られていないと美味しくても売れません。名前も知らないと注文もできないし・・・。
定番メニューに入れられないなら・・いらないヨ!と言わてしまうと、結局売れないです。
④小さかったり骨が多くて食べるまでに手間がかかる
小さいとさばくのに時間も手間もかかります。特に工場などで大量に生産したい場合は大きい魚の加工が楽なので小型は敬遠されやすくなります。
ヒイラギは小さくて骨もありますが、カラっと上げてフライで食べればいい!等発想の転換が必要です。
⑤イメージが悪い
「サメは臭いわけではない」けれど、イメージ先行で食わず嫌いの人もいますよね。そんなことないのに。「外道だ」と釣った魚を海に捨てる(逃がしてしまう)例も同じです。
ドチザメ。お刺身もおススメ。
⑥たくさん獲れすぎた
いくら食べられるとはいえ、越前クラゲが、大量に網にかかると・・・・一匹150Kg×大量の処理は難しいです。網が破けないように逃がすしかないでしょう。
小さな魚も獲れすぎると加工できないので売れ残ります。昔は干物や煮干しなどにできる分しかとりませんでしたが、現在は冷凍保管もできます。
「コノシロ」は、自分でさばいて酢漬けにして冷凍すれば、とても安くいつでも刺身が食べられますが、手間がかかります。
値段によっては絞って魚油を取ったり、乾かして粉にして飼料や肥料にする場合もあります。
ただ、人が食べられる食料だったら、人が食べたほうがいいですよね。
沢山獲れる時期に冷凍しておいて、解凍しながら一年中食べる・加工する方法は現代だからこそできる方法です。
⑦大きすぎて邪魔!
約9Kgのツバクロエイ・・・一家族で食べるには3か月を要しました。
竜田揚げがウマイ!お店で小分けにして売って欲しいです。
⑧見た目が悪い・傷がついている!
他の魚にガブっと噛まれて歯型(キズとも言いますね)がついていたり・・・
↑歯型のあるカンパチ。おまけで大きいサイズを貰えたので嬉しいし、生きていた証拠と共に命を感じられる。
↑天然秋鮭3.8Kg!漁師さんvs鳥??
定置網から揚げた瞬間に鳥が食べたのか、眼以外はきれいなもので、ルイベでお刺し身の他、白子もメフンも鮮度バッチリで美味しく頂けました!
よく見るとクチバシで突いた跡が少し見えて、微笑ましい。
鳥につつかれても表面を水でザザッと流して熱を通せば問題なし!
普段は魚の目玉を食べないくせに、完全を要求しないでよね!と言いたい!
⑨運ぼうとすると、傷をつけて商品価値を無くしてしまう!
ハリセンボンやギマのようにトゲがあると、網の中や発泡スチロールの中で周りの魚に傷をつけてしまい、ほかの魚の商品価値を下げてしまいます。
トゲを漁師さんが切ってくれれば流通できますが・・・漁師さんが頑張っても、買い支える皆さんの力がないとそのうち流通させずに海に返してしまいます。
カワハギの仲間でとても美味しい!ギマについては「こちら」
⑩温暖化で知らない魚種が獲れてしまった。どうすればいいかわからない・・・
①に近いですが・・・今まで獲れなかった岩手や青森でタチウオが定置網に入ってしまい、食べ方がわからず未利用魚になっているという話を聞きました。
なんてもったいない!包丁でドン!ドン!と切って塩焼きで内臓ごと食べてください!と、キッチンバサミでバシバシッと切るだけで美味しい塩焼きが食べれるのに!と叫びたくなります。
まずは買って、「こちら」のような形で楽しみましょう!
未利用の部位??
有名な魚でも人が食べない未利用・低利用な部位があります。
頭や内臓でも美味しく食べられる場所はあります。
マグロの大トロは今でこそ高級食材ですが、江戸時代は冷蔵技術が発達しておらず、すぐ悪くなるため、煮込みで食べられる以外は捨てられて(捨てると言っても肥料になる場合がほとんどだったようです)いました。
このように時代や技術によって、美味しい事がわかって高値で売れるようになる場合があります。
部位も上手に残さず食べることが海の資源を守ることにつながります。
さばいたら見つかる「白子」を捨てていないですか?
未利用魚・低利用魚を少なくする工夫
流通の工夫
鮮度がすぐに落ちてしまう鮮魚は、なるべく無駄にならずに速やかに販売されるためのシステムができています。
市場は全てを受け入れます。ただし、買う人がいないと値段は下がるので、期待した値段で売れずに損をする場合があります。誰かが損をすると、何度も損をしないように売れない魚は・損をした魚は獲らない・買わないようになります。自然に売られない魚が出回らないようにできているのです。
逆に、人気が出ると相場(値段)が上がって予約が入り、出回るようになります。
珍しい魚が美味しかったら買ったお店に「美味しかったからまた食べたい!」と言っておくことをおススメします。
漁師さんの工夫
魚を獲る場合は、小さすぎる魚が獲れないように網の目を大きくしたり、赤ちゃんのカニが逃げられる逃げ場所を作ったりして、大きく成長してから獲れるよう、海の資源が無駄にならない工夫がされています。いちいち逃がすのも大変なのでそのように工夫が進みます。
魚種を選んで獲る工夫もあります。季節や深さによって獲れる魚が変わるので、経験で狙えるようになります。そうする事で混獲と呼ばれる、狙った魚以外が取れる事を防ぎます。
もちろん、そのような工夫をしていても、取れてしまう魚もいるため、水中カメラで獲りたくない小型のマグロを逃がすようにできないか等、研究も進んでいます。
海上投棄している?
網の中に大型クラゲが多く入った場合などは、重すぎて網を上げる事ができず魚も触手で弱っているため逃がす場合があります。
クラゲがいなくても、売れない魚が多く入っている場合は、生きているうちに少しでも早く逃がすようにしている場合が多いようです。
捨てている?とんでもない!貴重な資源として利用されています
陸で「捨てる」と表現されている場合、多くは飼料や肥料になっている事がほとんどです。
例えば魚市場ではほぼ全てが集められて飼料向けになります。また、魚屋さんでも内臓や皮などを飼料屋さんが一軒ずつ回って回収している場合が多いです。「捨てている」つもりでも、上手に利用されています。
昔はお金を払って持っていてもらっていたこともありますが、今は飼料屋さんがお金を払って内臓を持って行きます。そう考えると、「捨てているわけではなく、実際は売っている」とも言えます。
魚の油はDHAやEPAが多く含まれるので、マグロやカツオの頭はグツグツ煮て魚油を取ります。健康食品、結構高いですが、カツオブシにするためにぐつぐつ煮た後の油や、刺身後の残った頭から取って精製しているのです。
未利用魚・低利用魚の利用例
人が食べられない魚たちも、人の技術や工夫によって立派に利用できるようになった例があります。
①鮮度がすぐ悪くなり、冷凍するとぼそぼそになっていたスケトウダラ
⇒冷凍スリミ技術を作り、カマボコ、ちくわなどの原料に。
②殻が柔らかいエビ(脱皮直後)
⇒「ソフトシェルシュリンプ:殻が柔らかいエビ」として頭ごと全身食べられるエビとして販売
③小さい魚が沢山獲れる
すり身にして練り物にしてさつま揚げなどに。骨もなくなって食べやすい!
おすすめの未利用魚
見てカッコイイ、スゴイ!キレイ!だったらそれがおススメ!
魚のさばきかたは基本は一緒。トゲだけ気を付けて知らない魚も積極的に食べてみましょう。
たまに毒がある魚などもいるので、自分で判断せず、市場を通った魚などプロが安全だと考えて売っている魚がいいでしょう。
有名でない魚も食べて欲しい理由
①皆さんの食生活が豊かになります。色々な魚が食卓に上がると話題も増えます!
なにしろ楽しい!↓都内の魚屋さんで・・・ユメタチモドキ。深海魚?メがクリクリ!
②地域が元気になります。漁師さんや加工屋さん、お店の人の収入になって、将来の仕事になります。
若者が仕事として漁師さんを選び、その地域に住むことにつながると町も若返ります。
③メジャーな魚の資源を守ることになります。
まぐろしか食べていなかった人が、地魚好きになると、人気がまぐろ資源に集中しなくなります。
④海外の魚介類が「買い負け」で買えなくても国内の魚なら活用できる!
日本の経済を守る事にもつながりそれが自分の将来の仕事になる場合もあります。
人気が出ると値段が10倍以上になって買えなくなっている魚介類も多いのです・・・「海外勢との買い負け」と関係がない国内の魚を上手に食べましょう!
⑤本当は食べたい魚介類を守ることにつながる
例)ツメタガイはアサリを食べてしまう→ツメタガイを食べればあさりは増える??
→砂だけ注意してさばけば結構おいしい!「ツメタガイのさばき方」もどうぞ!
他にもいろいろないい事があると思います。
そもそも、「多くの種類の魚が獲れるのが日本の海の特徴!」です。海に囲まれた豊かな海を受け入れましょう!
実は美味しいけれど知られていない魚介類はたくさんあるので、食わず嫌いにならずに興味を持って食べてみてくださいね。
未利用魚を買いたい!
「こちら」では、各地の様々な未利用魚が紹介されています。
連絡先もあるので、興味があれば直接連絡して購入条件を確認して下さい(一尾!などではなく、業務用が多いと思いますが条件次第だと思います)。
全種分かる人はナカナカいないので眺めるだけでも豊かな日本の海を実感できます。
キハダの胃袋のような部位の紹介もあれば、シュモクザメ、アオザメなどのようなイメージで食べられ得ない魚種もいますが、中にはマダイも。
理由は・・・大量に獲れると・・・価格が暴落してしまうのです。
温暖化で未利用魚は増える?
一人一人が魚に目を向けて食べてくれないと・・・・増えてしまう可能性が高いです。
水温が暖かくなると、今までと違う魚があなたの近くの海で獲れるようになりますが、名前を知らなければ・・・食べない人が大多数。
温暖化の影響で、北海道では鮭の代わりにブリが、石川でブリの代わりにサワラが漁獲されるようになっています。
獲られた後、北海道のブリは本州に運ばれ、石川のサワラは関西に運ばれているのが現状ですが、近くで獲れた魚を食べればいいじゃない!という意見も。
「ブランド魚も美味しくて素敵な魚達」ですが、これからの時代は「知らない魚でも積極的に興味を持って食べる!」ということも上手に海の資源を利用する方法の一つです。
※未利用魚は何でもかんでも食べていい?
現在は、肥料にしたり海に戻していたりしていた、人が上手に利用できていなかった分の魚たちを人が利用する形にしようとしている段階です。
未利用魚がバンバン売れるようになれば・・・・今まで以上に獲るようになる可能性がありますが、魚資源が一気に減る可能性も考えなければなりません。
今のところは、今まで通り取っていた分の需要を高めて価格を上げて、地域経済が元気になる、ぐらいまでなら問題なさそうですが、次の段階では漁師さんそれぞれが地元の魚資源が減らないようにコントロールをしていく取り組みも重要になります。一般的な魚の守り方の例は「こちら」。
テトラポッドを沈めて強制的に漁ができなくなる例は、持続的な形になり面白い取り組みです。
このように地域によって考えられているのです。
※未利用魚をタダで提供してほしい!
消費者としては感じてしまうこの気持ち。
運んでさばいて倉庫に入れるとお金が発生してしまう、漁師さんや加工屋さんは逆の考えで、少しでも高く売りたい!と考えています。このせめぎあいでモノの値段が決まります。
最初はタダで貰ったとして、永久には続きません。美味しかったら・・・価値があると考えてお金を払って、お互いが続けられる落としどころを探ると持続可能な形が見えてきます。
実際に食べてみた例
私は・・・漁師さんも絶賛、東京湾で一番美味しいと噂のツバクロエイの刺身を食べたい!と気になっていました。
ツバクロエイを、さばいた例は「こちら」から。
大人だけでなく、よいこにも知ってほしい!
子どもたちにも知らない魚の楽しさを知ってほしい!さかなクンがアカヤガラについて紹介。
メディアさんに協力!
未利用魚に興味を持ったメディアさんに全面協力しています!
2024年12月23日 徳島新聞 とくしまSDGsAction
2024年5月15日 読売新聞関西版夕刊
2024年4月号 公益財団法人 渋沢栄一記念財団機関紙「青淵」901号
未来に向けた水産物の利用:「未利用魚・低利用魚」
2023年10月26日 「読売KODOMO新聞」 未利用魚特集 取材協力
2023年10月22日 「東京新聞(中日新聞)サンデー版」 未利用魚特集 取材協力
2022年8月11日 札幌テレビ「どさんこワイド」
動画は・・・「こちら」からどうぞ。
2021年11月8日 シブ五時 未利用魚の解説
もったいないを考えよう~教えて未利用魚~ 動画の紹介
横浜市教育委員会、よこはま学校食育財団、横浜市中央卸売市場魚食普及推進協議会が連携して未利用魚を利用した給食と一緒に紹介した動画です。
普段は入れない市場の様子が見れるシーンも!
「フードロスや環境に関係したページ」も参考に、豊かな海を皆さんの手で守っていきましょう!

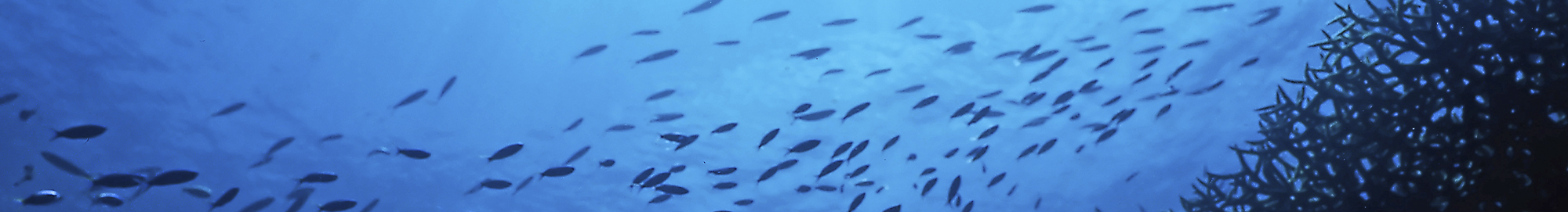





.jpg)




















