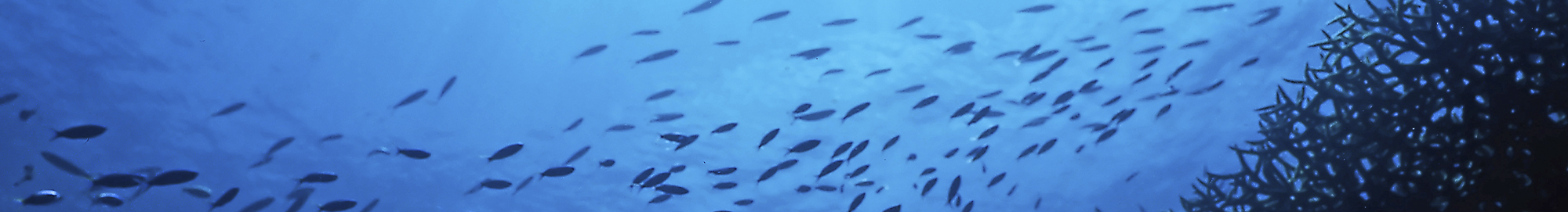イカナゴとコウナゴとキビナゴと・・・
この季節になるたびに調べては忘れる・・・私のような人のためのページです。
まず、「ナゴ」は小さい魚という意味です。
イカナゴ(玉筋魚、如何子)とコウナゴ(小女子) イカナゴ=コウナゴ
呼び方が地域で違うだけで、同じ魚です。関西ではイカナゴ、関東ではコウナゴと呼ばれます。
稚魚がどの魚の子どもかわからず、如何な子(イカナコ?)と呼ばれたとか。
関西ではシンコ(新子)とも呼ばれます。
イカナゴとキビナゴ
名前が似ているので混乱しますが・・・別の種類です。
住む場所、調理方法が異なるので見ていきましょう。
キビナゴ(帯小魚)
生息域:外洋に面した沿岸域、鹿児島等で獲られます。↓鮮度がよいと刺身用も!
鹿児島では幼魚時代の模様である帯をキビと呼ぶことからキビナゴと呼ばれたとか。
料理例刺身や天ぷら、一夜干し、唐揚げなどです。
イカナゴについて
生息域:内湾の砂地で生活し、瀬戸内海、日本海沿岸等で獲られます。
旬:2月に漁が解禁となり3月頃にお店に並びます。
料理方法は、鮮魚ではなく煮たり乾かしたり、鮮度が落ちる前に一気に加工する方法が多いです。
くぎ煮:関西では春の年賀状とも呼ばれるほどで釘煮を親しい人に送る風習があるようです。
チリメン:茹でて釜揚げ後に干したものです。
イカナゴ(コウナゴ)の不漁の理由・原因
地域によって理由が変わりますが、兵庫県で獲れなくなっている可能性を紹介します。
海がキレイになりすぎて?イカナゴが獲れなくなった?
魚が大きくなるために必要な餌であるプランクトンは太陽光と栄養塩類です。
キレイに見える透明な水が自然に優しいとは限りません。魚やノリが獲れなくなった原因が生活排水などが綺麗になりすぎた事と関係していることが分かったため、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部が改正されました「こちら」。
濁りと汚染は違うので、キレイだから海が豊かとは限りません。
同じ海域で育つ「ノリが不作の原因」も参考にどうぞ。
生活場所(産卵・夏眠場所)が無くなって獲れなくなった?海砂利の減少
イカナゴは6-12月頃に砂の中で夏眠しながら卵を成熟させ、12月から1月に砂に産卵します。
夏眠は冬眠と同じようなもので、活動をせずに代謝を抑えて休みます。
砂が無いと、夏眠できずに死亡率が高まると考えられますし、砂が無いと産卵ができません。
過去に、この砂(海砂利)が埋め立て・建築用骨材として使用された経緯があります。
昭和43年から平成11年の約30年で7.3億㎥が採取され(こちら)、そのうち瀬戸内海沿岸からは約6億㎥が運ばれたと考えられています。25mプール(25m×12.5m幅×深さ1m)、190万杯分です。
現在は海砂利の採取を全面禁止とする府県が多くなっていますが、採取を停めても砂利が溜まるまでには長い年月が必要となります。
獲りすぎ?
禁漁や漁獲時期の短縮化などの例もありますが、基本的には生き物は生活する場所と食べ物があれば、人が多少とっても減りません。
ただ、上記のように生活場所と食べ物が減っている状態であれば、人による漁獲が資源量の悪化に追い打ちをかける事になります。令和5年水産庁イカナゴ瀬戸内海東部系群資源管理の基本的な考え方は「こちら」
忘れない覚え方?
「コウイカは釘で干す!」
コウナゴとイカナゴは同じ種類。クギ煮のような加工品として食べる、と覚えてくださいね。
同じように似ているけれど違う似たものシリーズ 他の話題は「こちら」から!