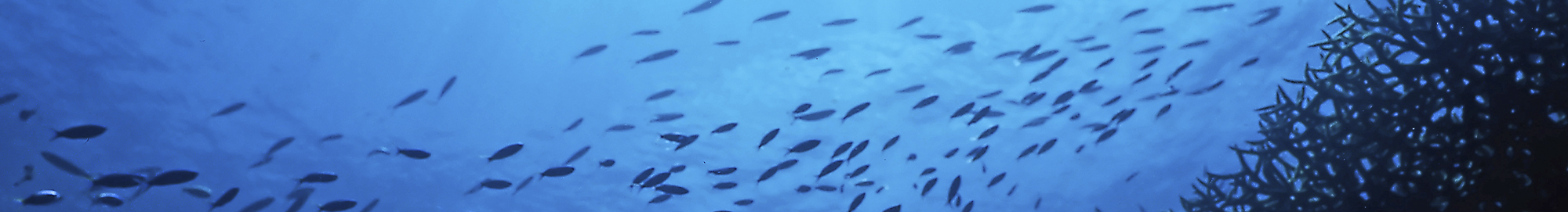魚の刺身は新鮮なほど美味しい? 目で見て、旨味をATPから考える
さかなの鮮度
取れたての魚は鮮度が良いのでオイシイ!とよく聞きます。
魚は鮮度が命とも聞くので、やはり鮮度が大事ですが、新鮮なほど美味しいのか?寝かしたり熟成がウマイと聞くのはどういう事??という魚の面白さを理解し始めている方はお付き合いください。
小難しい話ですが、頭で少し理解してから魚を見て、選んで食べると、違った面から美味しさ・旨味が見えてきます。
今日買ったそのサクを明日食べるとどうなるのか?自分の好みもわかってきます。
目でわかる魚のおいしさ?
歯ごたえや旨味を視覚で確認できます。
生きていたスズキを締めた後に、頭だけを掴んで撮影。背後の壁には当てておらず、ブランブランします。
スズキ 締めて2時間
縦横無尽に方向転換しながら泳げる柔らかさがそのままで、お刺し身にすると柔らかそうと思う人も多いでしょうが、この状態でさばいて刺身にして食べてもやわらくありません。
薄く切ってもブルブルの硬さが感じられるぐらいの食感が特徴で、人によっては噛み切れません。
うまみは少なく、硬さを楽しむ感じのお刺身の完成です。
釣り魚や活魚で試せるので、硬さが好きな人はチャレンジしてみて下さい。
スズキ 締めて26時間後
上のスズキのヒレとウロコを取り、内臓を抜いた状態で冷蔵庫に入れておいた、上と同じ個体です。
死後硬直のため、頭を持つとピンッと立ちます。凍っているわけではありません。
刺身にして食べると、〆直後よりは柔らかくなっているけれどまだ硬めの食感です。
※生き締めの魚は、内臓を抜いて真水で洗ってから水分をふき取りながらしっかり冷やすことで、1週間程度はお刺身で楽しめます。徐々に身質の硬さがやわらぎ、旨味が出てくる様子がわかります。
死後硬直終わり
さらに時間を置くと、死後硬直がなくなります。
体はそれなりに動くけれど、締めて2時間後のように縦横無尽の動きにはなりません。
魚種にもよりますが、このあたりから刺身にすると柔らかさが出てきます。
ヒガンフグ(関東ではアカメフグとも)は、さばいて1週間程度寝かせておかないと硬くて食べられないなど、魚によっても違います。
スーパーなどで並んでいる魚は、死後硬直が終わったあたりの魚です。
もしも死後硬直している状態のアジが並んでいたら、鮮度がいい!と判断できます。
自宅でもできる!プチ熟成!
ちょっと試してみたいけれど、釣りも活魚も縁遠い人は、タイやブリの「サク」を買ってきて、半分だけ今日食べましょう。残りは明日。翌日は柔らかくなってうまみが増えている事がわかります。
キッチンペーパーを巻いて余分な水分を吸い取りながらだと美味しく食べれますし、乾燥昆布をペタッと貼って一日待っても美味しいですよ。
「こちら」からカツオの叩きを一段美味しくして見て下さい!
結論 どちらがウマイか!
「人の好み」が結論なので、両方とも食べ比べてお好みの条件を試してください。
旨味や柔らかさを楽しみたい人は、ちょっと寝かせたぐらいがいいでしょう。
硬さや歯ごたえが好きな人は鮮度抜群の魚を。
豊後サバ活魚のお造り。5分前は泳いでいた??ブリブリの食感が最高!
旨味とは?
昆布のグルタミン酸、カツオブシのイノシン酸、干しシイタケのグアニル酸が3大旨味成分と言われます。
魚の刺身のうまみは・・・イノシン酸です。そのイノシン酸をどうにかして増やすと旨味が多いお刺身になります。さてどうしたらいいのでしょうか?
理由を化学的に考える!
化学が嫌いな人も、おいしさのために頑張って下さい。何となく理解したつもりでも十分です。
ATP(アデノシン三リン酸)は、人を含めて動物が動く時のエネルギー源です。
アデノシンにリン酸が3つ結合している状態の、結合している部分がエネルギーの貯蔵庫、これが離れる時にエネルギーが発生します。
リン酸結合が一つはずれると、ADP(アデノシン二リン酸)となり、エネルギーが発生します。
さらにはずれるとAMP(アデノシン一リン酸=アデニル酸)となります。
この後AMPはIMP(イノシン酸)に分解されます。
せっかく旨味成分ができてもその後時間が経つとイノシン→ヒポキサンチンに分解されて、最終的には腐敗してしまいます。
このタイミングが分かれば、旨味が一番多い時にお客さんに出せます。
高級なお寿司屋さん等は、このベストな状態を見極めてお客さんに出しています。
「ATP→ADP→AMP→イノシン酸→イノシン→ヒポキサンチン」の順です。
化学で1,2,3,4,5,をモノ、ジ、トリ、テトラ、ペンタ・・・と覚えた人は思い出してください!
ん?暴れた魚はどういう状態?
暴れるためにATPが分解されてエネルギーになってしまい、旨味の元が少なくなってしまっている状態になります。分解された後だとプロが寝かしてもなかなか狙ったうまさにはなりません。
そのため、釣った魚を一晩いけすで寝かしてから締める場合もあります。釣りで暴れた魚の体に増えたADPがATPに戻って暴れていない状態として出荷できるためです。
釣ってすぐに、おいしさのために素早く締める場合もあります。
頭をグサッと指す場合もあれば切ってしまう場合も。
頭と尾を切られたマツカワガレイ。暴れないようにする事と血抜きの目的がある。
神経締めとは?
脳を締めても神経が残っていると筋肉が動いてしまい分解が進むため、神経締めをすることで分解を遅らせることができます。
頬の傷でエラから血を抜き、頭からワイヤーで神経締めされているサワラ
鮮度が落ちた魚は美味しくない?神経締めが必要?
旨味か歯ごたえのどちらを求めるか、そして何の料理にするか、値段も大事です。
締める手間がかかる分、お値段も高くなります。そもそも大量に取れた魚は1尾ずつ手間をかけている時間はありません。
塩焼きや煮付けを家族で食べるなら、氷で絞められたアジやサバで十分美味しいです。
お刺し身で旨味を求めるなら釣ってすぐよりも内臓を取って数日ねかしたり考えてもいいでしょう。
ということで、鮮度がいいからと言ってオイシイ化は人それぞれ。
魚の購入段階から料理をイメージしているプロは、一尾ずつ味をチェックしながら一番美味しい瞬間を準備できるので、常に活魚を仕入れる場合もあります。
我が家はどうしようか。そんなことも考えながら家でどこまで美味しく楽しめるか考えても楽しいですね。
魚をさばく!
ATPとうまさの関係が分かれば同じ魚でも違う味が楽しめます。
さらにどんな魚でもさばけるようになれば、料理の楽しみ方は無限大!
さばくときの楽なコツは「こちら」からどうぞ!
ヒレを落とすと雑菌も増えにくくなり熟成しやすくなりますが、包丁でヒレを切るのは・・・大変ですヨ。