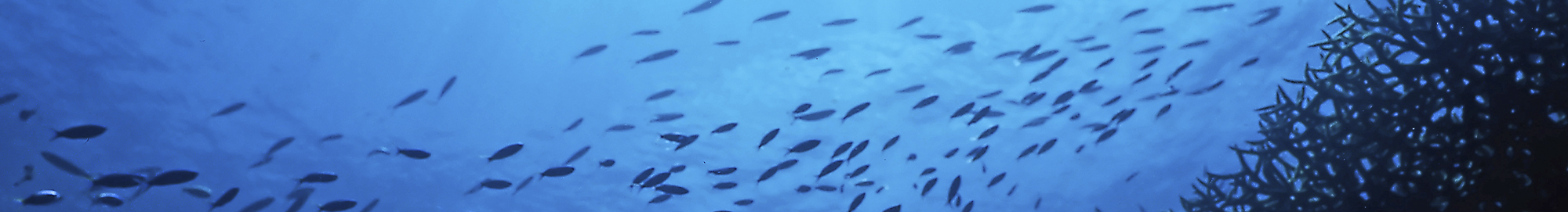オオズワイガニ?ホンズワイガニ?ベニズワイガニ? 何がどう違う?
日本でズワイガニと言えばホンズワイガニ(オピリオ種)
日本海に多いホンズワイガニ。
加能ガニ、松葉ガニ、越前ガニ、間人ガニ等の高級ブランドとなっています。
水深200-400m等の泥の海底にすみます。
雄の甲羅は15センチぐらい、雌はその半分ぐらいで大きさが違います。
↓上が小ぶりの雄、下が雌。
メスはセイコガニ、セコガニ、セイコチャン等と呼ばれていますね。
ズワイガニは各地でブランド化が進んでいます。地域やブランド名を知りたい場合は「こちら」へ!
日本海で取れるベニズワイガニは赤さが特徴。お値段も庶民の味方!
ホンズワイより深い海底500-2000mに住むベニズワイガニは生きている時から赤いのが特徴です。
殻を剥いた際の身の表面も赤く美しいので、カニチャーハンやカニ雑炊等に棒肉を入れると鮮やか。
加工原料としても大活躍です。
スーパーでも見かけることが多く、ケガニ等と比較して買いやすい事も庶民の味方です。
オオズワイガニとズワイガニの違いである口は、ズワイガニと同じまっすぐタイプ。
オオズワイガニ(バルダイ種) 海外から輸入しているのがメインだった
オオズワイガニはホンズワイガニより大型になるズワイガニです。
お正月に見かける脚だけのオオズワイガニはアラスカでトロールによって取られている子たちが日本に入ってきています。
アラスカではホンズワイも獲れますが、オオズワイは浅場で獲れて、ホンズワイガニよりも数量が少なく大きくなる事でオオズワイの値段の方が高いこともあります。
繊維(肉質)がしっかりしているタラバとホンズワイの間のような身質というイメージで、好む人も多いです。
ちなみに、輸入されているオオズワイは、脚だけが多く、カニ味噌は楽しめません。
国産オオズワイは、東京でも生きたままで出回ることも多く、頭が付いているのでゆでたり蒸したりでカニミソも楽しめるのが大きな違いです!
オオズワイガニ(バルダイ種)が北海道で獲れ始めた理由
2023年頃から北海道の襟裳岬や内浦湾(噴火湾)でオオズワイガニが獲れたというニュースが聞かれるようになりました。どちらの地域も水深は100メートル程度で、オオズワイガニが住みやすい水深です。
海洋環境の変化(潮の流れや、温暖化による水温の影響)によって、水深100mより浅い北海道沿岸で増えて獲れ始めた、という事でしょう。
海底を歩くタイプのエビやカニは大人になると移動できません。
でも、幼生(赤ちゃん時代)は潮に乗って移動します。
海洋環境の変化次第では、幼生が全滅!という事もあれば、生き残りやすい場所に集団で到着する場合もあります。
イセエビが福島で獲れているのと同じように、海洋環境の変化とオオズワイの住みやすい環境が合致したため、現在取れているという事です。
種類による漁法の違い
オオズワイガニ(水深100mぐらい)→ホンズワイガニ(水深200-400m)→ベニズワイガニ(水深500-2000m)の順に、深い場所に住んでいます。
オオズワイはカレイの刺し網に引っかかって獲れました。
現在は、カニかごで狙って捕っているそうです。
ホンズワイガニは底引き網で獲ります。
ベニズワイは深すぎるので網は無理!という事で、カニかごで獲ります。
このように水深によって漁法も異なります。
厄介者からの転身?
オオズワイが厄介者!と言われたのは、カレイ目当てで仕掛けた網に、邪魔なチビガ二がくっ付いて網が破れたりしたからです。手間ばかりが増えて邪魔!売っても二束三文。ケッ!
それが・・・大きいカニが引っ掛かれば、手間を考えてもニコっとして、浜の救世主!と反応が変わるわけです。
邪魔なチビガ二が安く出回り、買う人が増えて食べ方を覚えて、少し値段が上がっても食べる→売れる→漁師さんが獲る!という流れができたのもポイントです。
ズワイガニの成長速度
「こちら」のホンズワイガニ情報を見ると、雌は6年ぐらいで最大サイズとなり、その後最大7年生きるようです。
オスは8年ぐらいで最大サイズとなり、その後何年か生きます(メスと同じぐらいと仮定して最大15歳??)。
10回脱皮するまでに甲羅幅が60㎜ぐらい、孵化から10回脱皮までが雄雌とも6-7年ぐらいとのことです。
北海道のオオズワイガニの場合、漁獲されたカニの甲羅幅は、2023年頃は3-8cm、2024年は10cm、2025年は12-14cmとだんだん大きくなっています。来年はさらに大きくなる可能性があります。2023年に流れてきたのではなく、2020年頃には北海道の海に辿り着いていたか、常に生息していたのでしょうか。
なお、ホンズワイガニよりも浅い水深で生きるオオズワイガニの住む海は餌の量も多く水温も高いため、成長が速い可能性もあります。
ズワイガニは一匹のメスが10万粒も卵を産むと言われているので、現在の親が生んで獲れ続けると、これからも獲ることができます。赤ちゃんガニが生まれているか気になり、漁協さんに聞いたところ、2023年のような小さいカニも獲れているが、海に逃がしていて、来年以降獲りますよ。とのことでした。
カニかごは脱出口が付いていて小さいカニは逃げることができます。
厄介者が漁獲対象となり、邪魔だから獲ってしまえ!ではなくて取り尽くさないように守りながら獲る工夫がされ始めているので、来年以降もオオズワイガニが獲れる傾向は続きそうです。
オオズワイガニとズワイガニの見分け方:見分け方はM字かどうか!
甲羅のトゲが大きく、脚が太く短いので見分けられます。
住む場所がホンズワイより浅瀬なので敵が多いことなどが影響しているのでしょうか。
まとまって獲れるのはロシアやアメリカで、タラバとホンズワイの中間ぐらいの味で美味しいがナカナカ手に入らない。殻がホンズワイよりゴツイ、と取り扱っていた人から聞きました。
他にも口の部分がM字だとオオズワイ、まっすぐだとズワイガニです。
下のカニのココ↓ ここがM字型だとオオズワイガニです。
↓分かりにくいので、ベニズワイの口の写真を。本ズワイも同様にまっすぐです。
値段も手軽なので、食べてみて欲しいオオズワイとベニズワイ。
口の中にある胃袋を外すと美味しく食べられます。
※さばき方は「こちら」から。セワタ、エラ、胃袋を外してそれ以外は全部食べられます。
タラバガニ
甲羅の幅が25㎝ぐらい、肩半分で1Kgを越えます。お正月などに脚だけで売られているのはこいつ。
足を広げると1mを超える大型種で、実際はカニではなくヤドカリですが味はエビカニと同じで美味しいのが特徴です。
北海道では水深200メートルぐらいで取れます。タラが取れるタラ場で取れるのでタラバガニ。
参考:種名と学名
ホンズワイガニ Chinoecetes opilio :オピリオ種
ベニズワイガニ Chinoecetes japonicus
オオズワイガニ Chinoecetes bairdi :バルダイ種
タラバガニ Paralithodes camtschaticus
オオズワイガニを、ズワイガニと言って売っていい?
ダメです。不適正表示として農林水産省が食品表示法違反として再発防止策の実施を支持しました。
日本ではホンズワイガニの方が価格も高いので、安いオオズワイをホンズワイガニと見せかけるのはダメなのです。
消費者を守る法律ですね。
その他カニ情報
殻と胃袋とエラ以外はすべて食べられる!
カニミソが好きな人は、必ず胃袋を取ってから食べてくださいね!
苦かったり酸っぱかったり、じゃりっとするのは胃袋の中まで食べてしまっているためで、知らないのはもったいない!です。
旨い証拠とも言われる、カニビルについてなどを紹介しています。