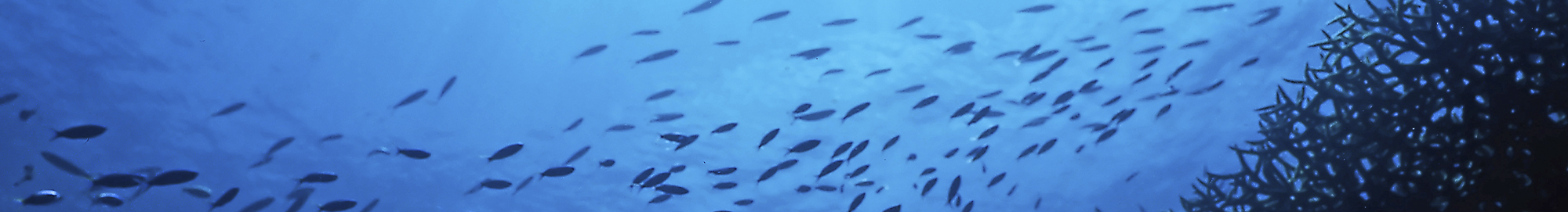牡蠣の種類 マガキとイワガキの違い
カキの種類の見分け方
岩からカキ取るから名付けられたとも言われるカキ。
殻を剥かれたり、半分剝かれてから冷凍されていたり食べやすくなっている事が一般的です。
有名な種類は、マガキとイワガキ。他にも日本では、イタボガキ、スミノエガキ等が生産されています。オランダから持ち込まれたヨーロッパヒラガキも東北で自生しています。
主な種類の殻の特徴を見ていきましょう(個体によって形は変わります)。
マガキ
旬は秋から春。細長い貝殻で、内部はチョークのような質感です。
東京湾では、泥の中に埋まっていた昔の殻が打ちあがるのです。30㎝!
イワガキ
夏が旬で丸い個体が多く、岩などにつき最大20㎝、1Kgにもなります。
大潮の干潮で普段より潮が引いた場所で発見。直径10㎝、高さ7㎝程度。
この子は漁業権が設定されている場合は、勝手に獲ってはいけません。
食べたい時はお店が安心!うまかった!
ヨーロッパヒラガキ
シーフードショーのノルウェーブースで見せてもらいました。平べったく、薄い形です。
1952年にオランダから持ち込まれ、2000年ごろまで北海道、青森、岩手、宮城などで養殖されていましたが、効率が悪いため撤退したようです。
現在も三陸の海に一定数定着しているようで、水温30度を超えても生育できるため、温暖化の影響で死ぬ例「こちら」への対策として、今後見かける機会が増えるかもしれません。
三倍体のカキとは??
通常のカキは染色体を両親からそれぞれ受け継ぎ2倍持った状態の二倍体(にばいたい)です。
品種改良で生み出された三倍体(さんばいたい)のカキは、産卵できない分、卵に栄養を取られません。
産卵後に痩せる夏でも出荷できるのが三倍体カキの特徴です。
また、「夏に痩せない=体力が残っている」状態なので、暑い夏を乗り越えやすいと考えられています。
牡蠣:生食用と加熱用の違い
同じカキでも全くの別物!
「こちら」で生食用と加熱用の違い等を知り、潮の香りを存分に楽しみましょう!
カキはノロウイルスが怖い?
カキはノロウイルスのイメージが強いですが、実は冤罪の部分も大きいのです。
ケーキでノロウイルスに感染!の理由は「こちら」
自分の身を守るためにノロウイルスの実態を知り、手を洗いましょう!
同じように似ているけれど違う似たものシリーズ 他の話題は「こちら」から!