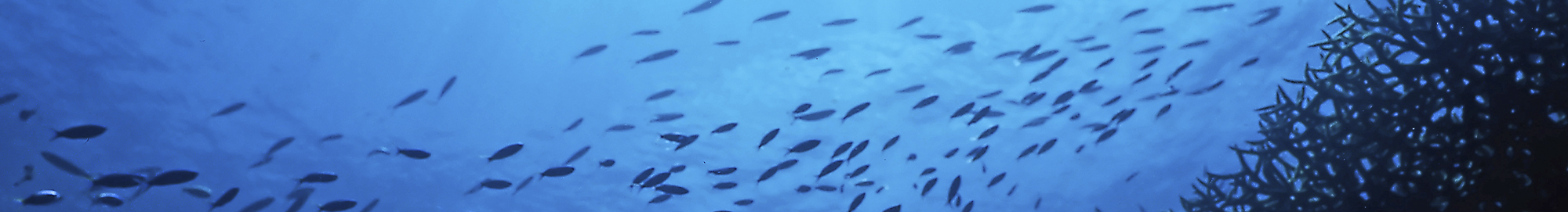クマの被害増加は温暖化も?海との関係から原因を考える
25年前にツキノワグマの研究をしていた元研究者としての私見です。山も海も一昔前と状況が変わっています。海と山の共通点も考えることで地球全体を守る事につながるため、紹介します。
日本に住んでいるクマは2種類
ヒグマ:北海道(1.5~2.8m:オスは300-500Kg、メスは200-350Kg)
ツキノワグマ:本州(1.2~1.8m:オスは20-150Kg、メスは40-100Kg)
体格も大きく異なる2種ですが、小さなツキノワグマでも大人の男性よりも力が強い事、爪があることに注意です。
クマのヌイグルミや、花咲く森の道で出会うくまさんのように落とし物を拾ってくれるカワイイ存在とはかけ離れた存在である事を知ってください。
クマの爪の鋭さ・頑丈さ
クマは木の上にある果実やドングリを食べるために数百キロの体重を爪で支えながら木に登ります。
その後、地上に降りる時に爪でブレーキをかけるため、木の幹に爪痕が残されている事があります。
↓軽井沢の直径30cm程度のウワミズザクラの木に残されたツキノワグマの爪痕と削れた後。
指の先に彫刻刀やナイフが5本ついていると考えるとわかりやすいですね。
↓さらに・・・北海道の某大学演習林内で発見したヒグマの爪痕は・・・大きすぎました。
私はバスケットボールを片手で持てますが、その大人の手よりも大きいヒグマの手の平。
5本のナイフが付いた手で、大人4-5人分以上の体重のヒグマに叩かれたら危険です。
同じく北海道の羅臼にて。これはブレーキなのか、樹液目的なのか・・。
樹皮が盛り上がっているので、傷がついてからしばらく時間が経っている様子が分かります。
クマの人身被害
クマが人を襲う理由は主に3つです。
①防御 突然出会ってしまった場合に、身を守るため。
見通しの悪いカーブ、雨や風により音が聞こえにくい場合に遭遇する可能性が高まります。
子どもを守るために親は通常より攻撃的にある場合も。
②縄張り エサが獲れる場所に入り込んだ場合。
ご飯を食べて、まだ残っている場合にすぐ近くでお腹が空くのを待つ場合があります。
漂着くじらの近くに潜んでいる場合があるため、北海道では要注意と言われています。
漂着くじらについては「こちら」
③食料 種類・個体によっては、人を鹿等と同じ「餌」の認識になってしまう場合があります。
哺乳類はメスよりもオスの方が移動距離が長い傾向がある種類もいます。
また、個体差によって人里に出てきやすい個体と、山の中で過ごす個体等、性格や行動が異なることが多いです。いずれにせよ、生きるために楽をするのが生物です。
楽を覚えてしまい、労なく餌が手に入れば、民家に近い場所で生活するようになる個体、家畜を繰り返し襲ってしまう場合もあるので、行動によって分けて考える必要があります。
人身事故のニュースを聞くたびに胸が痛みますが、人の安全な生活が第一です。
人身事故
北海道の海の中では、トドが網にかかった魚を食べてしまう例もあります「こちら」。
人の生活も、生き物を守ることも大事で、聖域として守る保護(リザベーション)ではなく、人の生活との中間点を探る保全(コンサベーション)の考え方が重要で、漁業や農業は、まさに後者です。
ちなみに、山の中で調査する際は、トウガラシスプレーを持ちながら山に入り、クマスズを腰に付け、見通しが悪い場所に差し掛かるたびに、叫んで自分の存在を周囲に知らせながら移動していました。
もちろん、唸り声が聞こえたり、姿を見た時は速やかに安全な場所に移動する事を心掛けていました。
クマが人里におりてくるのは、温暖化の影響?
25年前の長野県軽井沢の場合、10月頃には雪が降り始め、ツキノワグマは冬眠に入り始めていました。10月頃になると山での調査は終了!と嬉しくも寂しくもあるシーズンでした。
最近のニュースからは、ツキノワグマの冬眠が遅くなっている様子が感じ取れます。
冬眠は、動かずにじっとするだけでなく、心臓の鼓動もゆっくりとなり、エネルギー消費を抑えて餌が少ない冬を乗り切るための省エネモードです。
周囲が暖かいと省エネモードが解除されてお腹が空くので、食料を探す必要が生じます。
人里でクマの食料になるのは生ごみ、農作物、果樹などで、匂いによって誘引してしまう事につながります。
11月中旬に東北地方でも冬眠に入らずにいるニュースを聞くと、海でも山でも温暖化の影響が出ているのでは?と感じてしまいます。温暖化により海の中では魚が北に移動している様子が分かりますが「こちら」、場所を移動できないクマの場合は、冬眠時間や食べる餌を探す様子が変わったりしていると予想できます。
民家に出てきてしまったクマは駆除?逃がす?
捕獲した後に山奥に移動して逃がす等、クマと人の共存を図る場合もありますが、言葉が通じない危険な動物の行動を変えられない場合は、どうするのがいいでしょうか。
↓民家近くに出てきてしまったクマに麻酔をかけて、個体識別と計測後に逃がす前の様子。
タオルは目をケガさせないため。首元に「月の輪」模様が見える。
逃がす際、人が襲われる場合があるので要注意でした。
これはツキノワグマで、ドラム缶2つをつなげて罠を作ったりしていました。
体が大きいヒグマは、ドラム缶3つをつなげたワナを運ぶのも一苦労です。
麻酔をする場合は獣医さんが必要なので、人手がかかることも忘れてはいけません。
人を集めている間に、襲われる人が出てしまったら・・・等も考える必要があります。
海の中では、魚の冬眠モードが解除されて磯焼けにつながる?
ワカメなどは冬の寒い時期に成長します。その時期は以前ならばワカメなどを食べる草食魚が冬眠モードで動かずエサも食べていませんでした。
ただ、温暖化の影響で水温が高くなり、魚達が冬も活動できる状態となることで海藻類を食べて磯焼けとなってしまう海域が増えています。くわしくは「こちら」
なお、温暖化により、クマや魚が動ける期間が長くなっても、海でも山でも食料の絶対量はそこまで変わりません。
つまり、温暖化の影響で一匹一匹の活動期間が長くなる事で、海でも山でも全体的に餌が不足してしまう事にもつながりそうです。
遡上したサケが森を育てる?
少し前の研究ですが、海から遡上した鮭が森や川に栄養を供給するという事が言われています。
サケもなるべく食べられないように、集団で一気に川を上ります。
クマは、サケを川から岸にあげて森の中で食べますが、より効率よく太って冬を乗り切るために、栄養のある内臓以外は残す場合もあり、それが他の動物や森の栄養になります「こちら」。
温暖化により鮭の遡上が少なくなった今、このような循環にも影響が出てくると思われます。
温暖化を少しでも防ぐために
山も海も人の生活も全てつながっています。
温暖化を防ぐために、一人一人が電気を小まめに消したり、食べ残しを無くしたり、地元で獲れる野菜や魚達を積極的に食べるようにしましょう。食べた事が無いような、「未利用魚」と呼ばれる魚達も食べてみてくださいね。