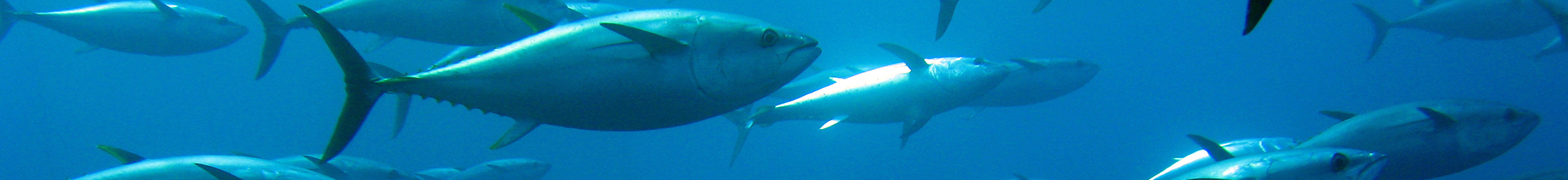鮮魚タッチ!魚を触る体験で魚に親しもう!
鮮魚(センギョ)とは?
凍っていない、生の丸魚の事で、頭もウロコも残っている生きていたそのままの姿。
その魚達が生きていた様子がわかる鮮魚を触るのが鮮魚タッチです!
都内20校で講師不在の鮮魚タッチを休み時間に実施してみたところ、平均234名の児童が参加、19校は再度実施したい!という反応だったので、このページを見ながら講師不在プログラムに挑戦してみてください!
鮮魚タッチの方法
海や魚を今より少し好きになるのが目的なので、苦手な人は無理しないこと。
魚をつかめなくても人差し指でタッチするだけでもOK。魚がダメなら貝は触りやすいかな?
身を守っている固い貝殻をカチカチ当てて音を聞いてみるうちに、さかなも触れるようになる事も多いです。
もちろん、魚をイキナリ触ってもOK。カツオ5Kgを持ち上げると、まるで漁師さんになったかのよう。
ただし!食べ物なので遊んだり乱暴にはしないこと。
「最後は先生が持ち帰って食べるから丁寧に!」です。
鮮魚タッチの準備
どんな魚でも楽しめます。10人なら魚1尾でも、アジ1尾とメヒカリ一尾などでも楽しめます。
小魚やワカメなどは、スーパーで買って冷凍しておいて、当日流水解凍でも楽しめます。
が、数十人規模の場合は発泡に氷を詰めてもらって、鮮魚ボックス形式で受け取る方がおススメ。
魚を買う方法や場所が分からなければ、魚屋さん、スーパー、学校給食納入会社さんに、聞いてみて下さい。頼むときのコツは「こちら!」
人数が多い場合は、サンマ・アジ・イワシを15匹ずつ!とか
天候によって天然魚は入手しにくくなるので、養殖ダイの予約もおススメ。
慣れてきたら・・・「1万円ぐらいで一箱お願い!10匹いれば十分だけど、色や形はイロイロで!」等とプロに任せると知らない魚が入ってくる可能性大!
「お、信用してくれたな。よし、任せとけ!」とプロがやる気を出します。
さすがに初めて見る魚の種類はわからないので、手板(ていた:魚屋さんで魚の名前を書いてあるあの板!)に産地と名前を書いてもらうのがおススメです。
※当日まで、届く魚がわからない場合もあります。我々が実施する場合でも、種名がわからない魚がいる場合があります。
図鑑を見ながら、この仲間?等と調べてもいいですし、種類はわからないけれど、色や形に着目して、そんな色になった理由を考えてみよう!と想像するだけでも面白いです。答えは一つではないので、わからない事がいくつか残るぐらいの方が、次につながる場合もあります。
魚好きのこどもが種類を教えてくれる事もあります。「先生達が知らない魚を僕は知っていた!」なんて、ずっと自慢できる誇らしい思い出になる事間違いなしです。
実施場所
基本自由です。タッチ後に手を洗うので手洗い場が近くの方が望ましいです。
少人数であれば家庭科・理科室の流しがスマートです。
数十人になるとブルーシートを敷いた広めの場所や、屋根がある外もおススメです。
気温には注意ですが、魚のウロコ、氷等々が多少散らかる場合もあるので、屋根がある屋外で計画すると掃除も楽になります。
鮮魚タッチのルール
自由に触ってOKです。特に注意せずに触らせてしまう場合もありますが、適宜下記をアドバイスする事もあります。
①怪我に気をつける
魚達は食べられないようにトゲがあります。ヒレの周辺、口の周りには注意。
最初にゆっくり触り、トゲがどこにあるか確認します(これはさばく時も一緒です)。
②食べ物です。遊びすぎない。楽しむのはOK。
先生が持ち帰るから投げないでね!潰さないでね!と伝えれば、多少は児童が落ち着きます。
③しっかり冷やしながら
先生が食べるので氷の上に置き鮮度を保ちながら実施します。
氷が冷たいのは当たり前。冬の海は寒いので、漁師さんはどんな思いで魚を獲っているのか・・・とか考える機会になるかも??
④苦手な人は無理をしない! でも触ってほしいので一言背中を押す言葉を!
苦手な人は無理は禁物。気持ち悪い人、これ以上は嫌いになりそうなら、見ているだけでも成長できます。
頑張れそうなら、貝や、魚のプニプニの目だけ指先でツンツン触ってみるだけでも大成功!
とはいえ、触ってほしいので・・・
匂いやヌルヌルが苦手な児童のために、「腐った匂いじゃないでしょ?海やお刺し身の匂いなんだって。」と伝えてみてください。魚の匂いは海の匂い!「ヌルヌルは、生きるため、泳ぐために必要なことで鮮度の悪さではないらしいよ!」のも重要なポイント。
⑤市場や魚屋さんでは絶対に触らないこと!
買ってから触るように!
⑥アレルギーの人は・・・・
アレルギーには個人差があるので、各家庭の判断次第です。
エビ解剖時の室内に入ることもNGという家庭もありました。
出前授業で実施する場合は、見学か、手袋を使って触ってみる(終了後しっかり手を洗う)が多いです。
さて、おまちかねの・・・楽しむコツ!
名前はわからなくても大丈夫。
それより、色や形など、色々あるな。不思議だな。と感じる事が大事です。
そして、答えや理由をすぐに知らなくても大丈夫です。よく見て触っているうちにわかることもあるし、魚の気持ちになって2-3日考えてみてから調べてると、ハッとわかることもあります。
分からない事を直ぐ聞かずに、じっくり触ってみてくださいね。
①ウロコを見て触る。
ヌルヌルしていたり、ザラザラしていたり種類によって違います。頭からしっぽ、シッポから頭に向けて触ってみよう。詳しくは「こちら」
ヌルヌルも早く泳いだり体を守る秘訣です。
②ヒレを広げる。とてつもなく大きかったり、派手だったり。詳しくは「こちら」
③口を開く・・・思いのほか大きく開く魚も。アジも、大きく開きますよ。
どれぐらい広がる?舌はある?水を入れたらどこに入っていきそう??
④歯を見る。歯が鋭く、返しが付いていて逃げられなくなっていたり・・・
口や歯について詳しくは「こちら」
⑤色や模様を見る。背と腹で色が違っていたり!
波のような模様があったり、
長い間生き残ってきた生き物の姿や形、色には全てに理由があるハズです。
色について詳しくは「こちら」
答えをすぐに知ろうとせずに、魚の気持ちになって2-3日考えてみてから調べてると、新たな発見が見つかる場合もあります。
レベルアップ!この上までは、説明なしでも子供が勝手に楽しみます。
ここからは、ちょっとウンチクを入れると大人も楽しめる例です。鮮魚タッチを何回か実施してから少しずつ覚えてください。
天然と養殖の鯛を1尾ずつ頼むと・・・違いがハッキリ判る!「こちら」
深海魚 目が大きくて色が様々。その理由は・・・「こちら」
口の中や表面、身にもいるかもしれない寄生虫。悲鳴が聞こえる事もあるけれど、知っておけば怖くない!「こちら」
飛ぶ魚トビウオ。ヒレだけじゃない飛ぶ仕組みは・・・「こちら」
エビの解剖をしたり。。。「こちら」
イカの解剖をしたり・・・・「こちら」
そろそろ・・・↓市場で見かけたカゴの中の魚は何種類?かわかるハズ。
魚だ!ではなく、アナゴ、カマス、タチウオ、ダツ、ヌタウナギ、タイの7種。
それぞれに楽しい発見があるハズです。
魚をさばいて食べたい!
その言葉を待っていました!
鮮魚タッチ中にしっかり冷やしながら触っていた魚は、加熱すれば食べる事ができます!
ハサミを使って怪我無く楽にさばく方法は「こちら」から。
一番カンタンなのは塩焼き。煮付けも美味しい。
塩焼きは、エラと内臓を取って、ヒレを切ってからアルミ箔を船のようにして中で焼いて、そのままお皿に移動すると掃除が楽です。焦げ臭さも少ないです。
学校では、子ども達に食べさせることは難しいので先生方が持ち帰って翌日どのように食べたか報告してください。子ども達が「ずるい!」と自分も買いたくなる事間違いなし!です。
遊び?教育?魚に親しむと、魚が取れる地域や水産業界が元気になる!
そもそもアジとイワシとサンマの違いが判らない人も多い世の中。
鮮魚で出回る有名な三種でさえ、名前がわからなければ、さばき方も、調理方法もわからず、買って食べようとする人は少ないでしょう。
・・・・これが、海に囲まれている日本が魚離れ一直線の理由です。
知っている・有名な魚しか食べないと、地元でとれる魚を無視する事になりもったいない。
見た事もない魚を触っておくことで、日本で出回る鮮魚600種以上をどれでも楽しめるようになるはずです。
温暖化対策にもなる、鮮魚への親しみ‼
知らない魚も食べると地元の生活や、海の資源を有効活用する事にもつながります。
そして、最近は今まで獲れなかった魚達が各地で獲れています。
温暖化の影響で今までよりも水温が変わったことでその水温が好きな魚が移動してくるのです。
知らない魚を食べない事は、目の前の海で獲れた魚を無視する事になってしまいます。
そんなことで、みなれない魚こそ、楽しい!見たい!と考えて触ってくださいね!
遠くから魚を運ばずに近くで獲れた魚を獲る事で燃料も使わずに済みますし!
さばきながら発見できる事も!観察!
さばいていると、胃袋の中に魚がいることも!鮮度がよければ食べてもOK。
↑マトウダイはこんなに大きなイトヨリダイを食べるのか!とビックリ!
美味しく食べる!
ノドに骨が刺さるのが怖い人は・・・「こちら」で予防と対策を!
楽しい鮮魚タッチをきっかけに丸魚を自宅で買う人が増えれば、お店に丸魚が並ぶようになり、周囲の人も魚を楽しめるようになるはずです。
「未利用魚」の活用にも関係してくるので、取ってもおススメの鮮魚タッチ。
一匹からでもチャレンジしてみてくださいね!